「デザイン批評はどこにでもある」への個人的注釈
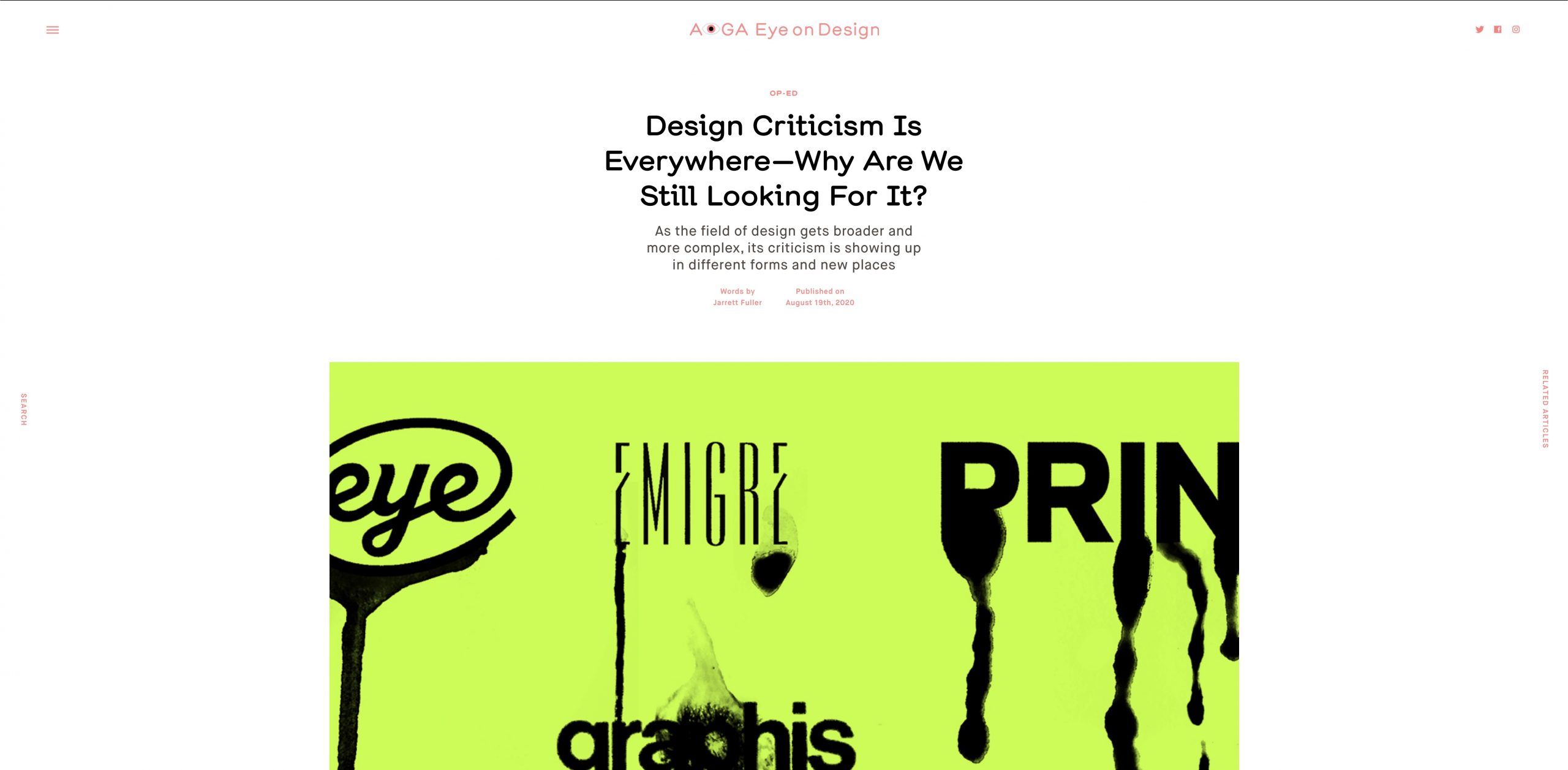
先だって掲載されたフューラー「デザイン批評はどこにでもある」で語られている内容の時代背景や、そこから振り返る日本の状況について本サイト編集長が補足的に語る。
欧米のグラフィックデザイン批評との出会い
ジャレット・フューラー「デザイン批評はどこにでもある──なぜ私たちはそれを求め続けるのか?」は、2000年代から現在にいたる西欧グラフィックデザイン批評の勃興とその変容について、著者の個人的な経験を交えて語ったエッセイだ。しかし、日本の読者にはそもそもどこの誰がデザイン批評を求め続けているのか、「私たち」とは誰のことか、と思う向きも多いのではないだろうか。この記事では個人的な体験の範囲であるが、フューラーの原稿の歴史背景について解説してみたい。
私は1999年から2018年まで『アイデア』というデザイン誌の編集に携わっていた。1953年創刊のこの雑誌は「世界のデザイン誌」をうたい、国際的な情報を日本の読者に伝えることをひとつの特長とした。同誌は日本のデザイナーが海外のデザイン情報を得る数少ない窓口として、戦後のデザイン界に並走してきた。
『アイデア』の編集部に入ったのは、MacintoshとDTP技術によるデザインのデジタル革命の熱狂がちょうど落ち着きはじめた時期だった。まだ、インターネットは大きな画像データをやりとりするほど回線が太くなく、デザイン関係の情報もとても少なかった。ネットは電子メールのための手段で、海外の情報は現地での取材や洋書、洋雑誌から入手していた。
本論で「ルネサンス期」とされている英米のグラフィックデザイン評論系出版物に最初に出会ったのは、取材で訪れたロンドンだったと思う。芸術デザイン系書店の店頭にはMacを駆使したテクノ〜グランジ系のグラフィック作品集が溢れていたが、それらと好対照をなすようにテキスト中心の評論書の棚が目に入った。
イギリスの出版物では評論家のリック・ポイナーと、1990年に彼が創刊した『eye』誌、タイポグラフィについてはロビン・キンロスのハイフン・プレスが同時代的な存在感を発揮していた。アメリカのものでは評論家のスティーヴン・ヘラーやエレン・ルプトンのようなデザイナー、教育者が活発な執筆活動を行い、西海岸の『Emigre』誌がしばしば論争の場となっていた。
こういった出版物を拾い読むことで、英米圏の「グローバル」な評論の書き手やテーマの輪郭が、おぼろげながら浮き上がってきた。日本のデザイン書はというと、デザイナーの自己宣伝的な作品紹介や技法書ばかりだったので、英米にこのような批評的なテクストの領域があるという事実には、素直な感銘を受けた。
批評の枠組みとその実践
そこでの議論には私の見るかぎり、互いにからみ合う大きく三つの文脈があった。まず、いわゆるポスト構造主義の思潮を背景にした、機能性、合理性、問題解決といったモダンデザインの前提への批判。次に、100年を迎えようとするグラフィックデザインの歴史の再検討。そしてデジタル技術がデザインと社会の関係にもらたすインパクトについての議論である。
これらの議論は同時代のグラフィックデザインとも響き合っていた。もはやデザインの「中立性」やデザイナーの「透明性」はただの神話にすぎないというかのように、若手のデザイナーたちはテクストの意味を攪乱するような脱構築的タイポグラフィや、過去のデザイン様式や土着的な視覚文化を自在に引用していた。
当時の私は、グローバル化やネットによって日本と海外の距離が近づいた今、先述したような海外の言説や実践の潮流を紹介することに「世界のデザイン誌」が果たすべき役割があるのではないか、と考えた。現実問題として、海外デザインの事例は図版を見ただけで了解できるものは少なくなり、その背景にある社会や文化のコンテクストを説明しないと理解できないようになっていた。
西欧のグラフィックデザインは記号や表象のシステムとその言語的な操作という側面を全面的に強めつつあった。そういったものを伝えるためにはビジュアルを「見れば分かる」という考え方はあまりにもナイーブで、デザインの世界観や歴史的文脈込みで伝える必要があった。
しかし、日本のデザイン言説はデザイナーの個性とその表現という構図に縛られていた。かつては日本でも、西洋のデザイン思想と日本のそれをめぐってさまざまな議論が交わされていた。だが、それはデザインという職能が「産業」として社会に定着するとともに棚上げにされ、2000年頃以降には海外のデザイン文化への興味は急速に失われていった。
表面的なグローバル化が進む一方で、日本と海外のデザインには根本の部分で大きな断絶状態がある、というのが私が最初に捉えた風景だった。『アイデア』ではそのギャップを埋めるべく、西洋のコマーシャルではない思想的なデザインの動きをしばしば紹介してきた。だが、それが直訳的な紹介にとどまったことは否めない。つまり、読者に納得してもらう仕掛けを展開できなかった反省がある。
オンラインコミュニティの発展
フューラーの論考では、彼が2000年代中頃に盛り上がったデザイン系の掲示板やブログを熱心に読んだことが語られている。これらのブログサイトについて補足すると、いわゆるエッセイや評論文を掲載するようなもの以上に、新着デザインニュースをひとつの編集方針によって選択・紹介するサイトが存在感を発揮した。
そのようなサイトが成立する前提となったのは、デザイナーが既存のメディアに頼らずネット上で自ら情報発信しはじめたことだ(とくに欧米圏では個人デザイナーのあいだで「Indexhibit」というコンテンツ管理システム を使ったポートフォリオが普及した)。ニュースブログはこれらのポートフォリオの投稿を引用・紹介することで成立していた。記事の内容は引用元の記述ほぼそのままなのだが、その「まとめ」行為はひとつの情報編集として価値を持った。
これらのなかには商業的なメディアとして成長していくものも現れた。引用なのか無断転載なのか分からない手つきはいかにもネット的で、掲載許可取りに手間を取られる商業出版物に携わるものとしてはうらやましいかぎりだった(もっとも、大手出版社のなかにもその黎明期にはグレーなまとめ的出版物で成長したところがいくつもあるのだが)。
ネットのデザイン系サイトやフォーラムの中心的なトピックとなったのはフォントやロゴの領域だった。90年代初頭のFUSEプロジェクトやEmigreのように、フォントデザインはMacの到来以降、先駆的なデザイナーがいちはやく取り組んできた領域だった。そこにやがてオーセンティックな書体設計の言説も合流し、ネットは主要な販売チャンネルであるとともに、書体設計やタイポグラフィについての知識や技術を共有する重要な場となっていった。
ロゴはデジタル化がもたらした情報環境のなかで急速に変革を迫られた領域のひとつだった。それまでのシンボルマークのような固定的で造形的なアイデンティティに代わって、さまざまな環境に動的に対応できるデザインプログラムが注目を集めた。掲示板ではとくに、企業ロゴのリブランディングの話題が熱い議論の対象となっていた。いまなお進行形のこのトピックには、従来のモダニズム的な造形中心の発想と現代のニーズの断層を浮き彫りにしている。
批評としてのプロジェクト
ネットからは、それ以前の「真正な」デザイン批評の文脈を引き継ぐような継続的な書き手も多く登場した。かれらはやがて小規模の生産、流通、決済システムの普及によって盛んになった自主出版の流れにも合流していった。この時期の出版物の方向性に影響を与えたものとしてはデザイン誌『DOT DOT DOT』を挙げておきたい。それまでのデザイン誌のフォーマットから逸脱した前衛的な文芸誌やアート誌のような編集方針は、一部の先端的なデザイナーに大きな影響を与えた。
関連して付け加えると、同じころ「横断的(trans-boundaryとかmulti-disciplinary)」という言葉が先鋭的とされるデザイナーを説明する定型句となった。つまり、デジタル環境を背景に、グラフィック、映像、ウェブといったメディアを横断し、さらには自主的な活動まで行う独立系デザイナーのイメージである。さらにはExperimental JetsetやÅbäkeのような、グラフィックデザインを「手段として」用いたアート的プロジェクトを行うデザイナーたちも現れた。こういった方向性は、グラフィックデザインがコンピュータを通じて民主化し、技法や効率の話題に収斂されていくデザイン観に対する、批評的なカウンターとしては生まれてきたともいえよう。
フューラーが描いたグラフィックデザイン批評の変遷を振り返ってみれば、まず出版物上の評論があり、そこからネット上のフォーラムやブログでの議論が発展し、SNS時代の到来とともにアノニマスな一般市民の声とデザイナーによる批評的な実践に大きく分かれたと要約できる。このデザイナーによる批評的なプロジェクトは、近年、実験的な志向を持つデザイナーたちが目指すモデルのひとつとなっている。それはまた、ヨーロッパや北米の「デザイン先進国」だけではなく、東西冷戦後のグローバル資本主義世界のなかでデザインに取り組みはじめた中東欧、東アジア、東南アジアをはじめとする全世界のデザイナーにも広がっていった。
最初からデジタル環境を前提としてデザイン産業を成長させはじめたこれらの「デザイン新興国」は、ネット上の知識やリソースを活用しつつ、グローバルなデザインの市場と言説に直接つながっている。ネットがかつてのような情報格差を解消する一方で、しかし、英語を共通言語とする巨大なグローバルデザイン世界への同質化が加速したようにも見える。とくに画像共有サービスの普及以降は、あるグラフィック・スタイルが思想ではなく雰囲気のレベルで伝播するようになっている。
同様に、世界各地の批評的な自主出版プロジェクトも奇妙に同じ雰囲気をまとっている。それらは、たいていの場合、リソグラフ印刷のような手法によるフェティシズムを帯びている。ネット時代にあえて物理的に閉じたメディアを作ることは、情報を選択的に伝えるひとつの態度だ。しかし、そこにはデザイン・オブジェクトとして自己完結する危険もある。書き手は増えているが、互いのテクストを参照しあう大きな議論が生まれにくい状態だ。
日本のデザイン批評はどこにある
フューラーのテクストはその結論で、20世紀末から21世紀初頭にかけて発展したデザイン批評それ自体が、ある時代状況に即した歴史的な産物であり、デザインという枠組みの社会的なあり方が大きく変わったことで、その語られ方も自ずと変化していくことを認めている。この点については全面的に同意できる。
その副題「なぜ私たちはそれを求め続けるのか?」にはそのような現実認識と、それでも他ジャンルのような批評のあり方にあこがれを抱き続けてしまうことへのアイロニーが含まれている。ただ、フューラーの見解は、欧米においてこれまで語られてきたデザインの批評的言説の積み重ねを否定するものではない。結局、この「私たち」に、やはり日本の私たちの多くは含まれていない。つまり、フューラーの副題は私にとって、ないものねだりという点で二重のアイロニーとして響くのだ。
事実、批評が成立する前提としての、日本のグラフィックデザインの歴史や理論への意識はとても脆弱だ。前にもどこかで書いたがこの状況を解消するための一歩は、「デザイン」という言葉を英語圏のグローバルな領域と日本語とで相対化して語る視点をもつことだと思う。まずは、日本が近代(modern)という時代のなかで西洋が数千年かけて練り上げてきた「design」の表面だけを移入したという事実を再確認することだ。
「近代」というテーマについて考えることは、さまざまな批評理論を駆使して語られる昨今の芸術や文化についての議論に比べて素朴な響きがする。また、日々アップデートされるビジネストレンドやテクノロジーの話題に比べて大時代的な雰囲気がある。しかし、デザインはまぎれもなくモダンという時代精神の産物であり、それがもっとも先鋭的に現れている領域だ。
そうやって語られる日本のグラフィックデザイン史は、明治以降の展開を日本列島の書字と図像の歴史全体の上に俯瞰するものとなるだろう。この態度は近年注目されている、西洋の歴史観の拡張ではない世界史をどう構築するかというグローバルヒストリー研究の潮流とも無関係ではない。
また、フューラーが「どこにでもある」というように、同時代のデザインのリアリティを考える視点や議論は、グラフィックデザインに隣接する学問領域や、職能としてのデザインとは直接かかわらない生活領域のなかにある(このような方向については2000年代に、戸田ツトム・鈴木一誌らの責任編集による『d/Sign』誌が豊かな材料を提供していた)。
日本のグラフィックデザインについての批評的基盤は、歴史の更新と現代の情報リアリティへの視点、その両方の間から生まれるはずだ。もっとも未来のデザイナーや書き手たちは、現代のこんな葛藤や閉塞をあっさり歴史の一コマとして処理して、自在な言説を紡いでいくのかもしれないのだが。
室賀清徳(むろが・きよのり)
編集者。グラフィックデザイン、タイポグラフィ関連の書籍企画、評論、教育活動にかかわっている。本サイト編集長。
公開:2021/07/21
 84
84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳
 83
83ワールドワイドウェブのこと/永原康史
 82
82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3
/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81
81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩
 80
80数学と計算機と美学/巴山竜来
 79
79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生
 78
78ひび割れのデザイン史/後藤護
 77
77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史
 76
76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子
 75
75日本語の文字/赤崎正一
 74
74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子
 73
73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部
 72
72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳
 71
71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史
 70
70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子
 69
69作り続けるための仕組みづくり/石川将也
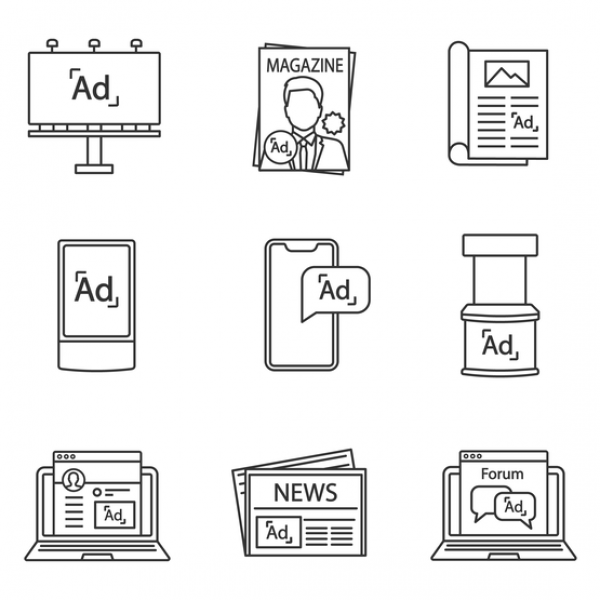 68
68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子
 67
67音楽の空間と色彩/赤崎正一
 66
66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳
 65
65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩
