デザイン批評はどこにでもある
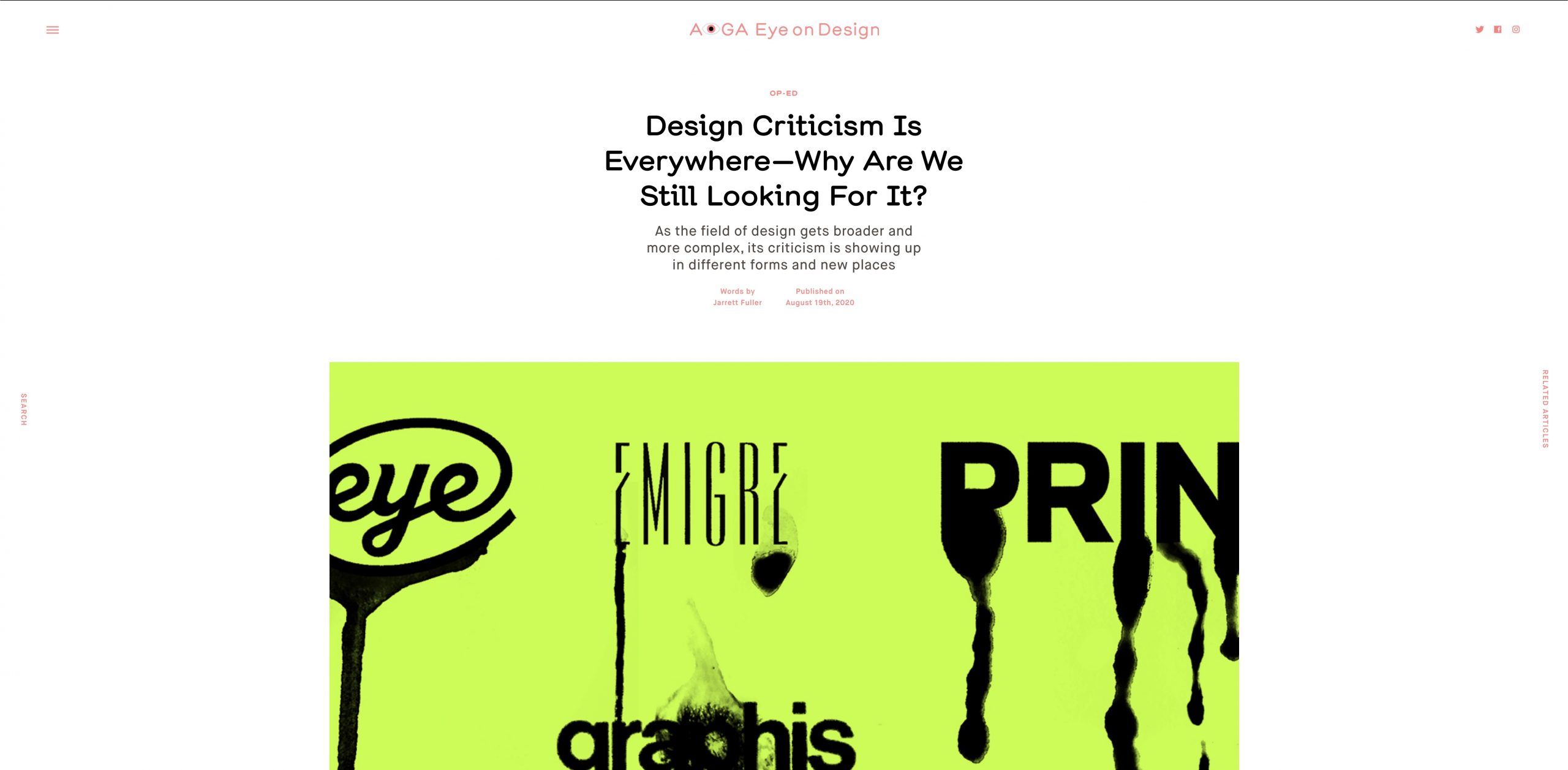
「グラフィックデザインには批評がない」とよく語られるが、ここで言うグラフィックデザインの批評とは何を指すのだろうか。2020年8月に「AIGA Eye on Design」に掲載されたジャレット・フューラーによる本記事は、1995年の『Eye』誌上でのリック・ポイナーとマイケル・ロックの対談を起点に、グラフィックデザインを取り巻くメディアの変遷を経た現在の「デザイン批評」について論じられた示唆に富むテクストだ。「グラフィックデザインの批評」は本当はどこにあるのだろうか。
私たちグラフィックデザイナーは批評と愛憎関係にある。私たちは、より多くの批評を求めながら、それが自分に向けられると文句を言う。一般の人びとに自分たちの仕事を理解してもらいたいのに、私たちの仕事についての記事が書かれると、それがどう間違っているかを批評してしまう。ビジネスの場で尊敬されたいと言いながら、「デザイン思考」のようなものが出てくると文句を言う。明確なコミュニケーション能力を売り物にしているにもかかわらず、自分たちが実際に何をしているのかを説明するのは難しいし、ましてや、自分たちが求め続けている批評がどのようなものであるべきかを明確にできていない。多くのデザイナーに「グラフィックデザインの批評とは何か」と聞けば、十人十色の答えが返ってくるだろう。
この質問は1995年の『Eye』誌に掲載された評論家のリック・ポイナーとデザイナーのマイケル・ロックによる今なお示唆に富む対談「グラフィックデザイン批評と呼ばれるそれはいったい何か(What Is This Thing Called Graphic Design Criticism?)」で、ポイナーが問いかけたものだ。「アートや映画の批評に比べて、『グラフィックデザイン批評』という言葉には聞き慣れない、少し居心地の悪い響きがある」とポイナーは語り始める。「グラフィックデザインの雑誌や書籍を熱心に読んでいる人でも、めったに出会うことのない言葉だ」。そして2人はデザインと書くことの関係や、どのようなデザイン批評を読みたいかについて話を続ける。ポイナーがデザイナーやデザインされたオブジェクトをより大きな文脈の中で捉える「ジャーナリスティックな批評」の輪郭を示す一方で、ロックは文学理論や記号論のような文化的な批評をデザインについての文章に適用することに興味を持っていた。
この対談が発表されたのは、一種のデザイン批評ルネサンスの真っ只中だった。ポイナー自身が発行していた『Eye』誌は、ルディ・バンダーランスとズザーナ・リッコによる同名のタイプファウンダリから発行されていたベイエリアのアバンギャルド雑誌『Emigre』と並んで、その代表的なデザイン誌だった。同じ頃、『Print』や『I.D.』などの雑誌(ロックは寄稿者の1人だった)がグラフィックデザインに関する批評記事を掲載するようになり、デザインを専門とする数少ない学術誌も登場した。その1年前には、デザイナーのマイケル・ビエルート、ウィリアム・ドレンテル、デザインライターでありデザイン史家でもあるスティーブン・ヘラーの3人が近年のデザインに関する優れた文章を集めたアンソロジー『じっくり見る(Looking Closer)』シリーズの第1冊目を出版し、その後10年間で5巻が刊行された。確かにこの時代は豊かな時代だった。1990年にMacintosh Plus用に850ドルで発売されたPhotoshop 1.0はデザインプロセスを高速化し、より複雑なレイアウトや新しい書体のデザインを可能にすることで[デザイン業への]参入のハードルを下げた。新しい美学に懐疑的なモダニストと、この新しいテクノロジーの限界に挑戦するポストモダニストの間で議論が重ねられた。それゆえ、ロックがポイナーとの対談の最後で批評の未来について楽観的な見方をしているのは驚くことではない。「私たちはおそらく、自己定義の問題として自分たちをグラフィックデザイン批評家と考える最初の世代の書き手であり、その始まりにいるという感覚はとても開放的だね」。
しかしながら、2013年に出版されたロックの単著『多数からなる署名(Multiple Signatures)』に掲載されたフォローアップ対談で2人が20年近くの時を経て再会したとき、明るい視点の楽観主義の多くは失われていた。ポイナーは「私たちはこれ以上、学術的な批評を求める漠然とした『呼びかけ』を必要としていないのではないだろうか」と語った。「行動が必要だ。さらにたくさんの批評と、それを発信する場所が必要なのだ」。ここでのポイナーの言葉は、1983年に発行された『グラフィス年鑑』の巻頭言を依頼されたマッシモ・ヴィネリが、その場を借りてより厳密なデザイン批評を呼びかけたことを彷彿とさせる。
「いまこそ理論的な問題が表明され、議論され、知的な緊張感の中から意味が生まれてくる場を提供するべきだ。見た目のよさでは、もはや私たちの視覚環境を形成する方法を導くことはできない。議論し、価値を探り、われわれの遺産の一部である理論を検証し、時代を表現するためにその妥当性を検証する時が来ている。言葉に耳を傾ける時が来たのだ」
建築家としての訓練を受けたヴィネリは建築をめぐる言説に憧れを抱き、グラフィックデザインにも同じことを望んだ。この思いは多くの人に共有されているようだが、過去30年間のデザイン批評をめぐる議論を前にするとポイナーとロックのオプティミズムは浮き世離れしたもののように感じられる。ヴィネリが切望したような、デザイン批評がもっと必要だ、という声には終わりがないようだ。スティーブン・ヘラーは、1993年にAIGAの『The Journal』誌における寄稿でこのように語った。「職業としての批評家をサポートできない職業は、次第に痩せ細っていく運命にある」。
ポイナーはさらに、2005年に「Design Ovserver」で発表した「デザイン批評家はどこにいる?(Where Are the Design Critics?)」という記事でこのように述べている。「どのようなかたちにせよデザイナーが真に批評的であるためには、意欲的かつ知的な態度に貫かれた批評を通じて、デザインに対する批判思考に継続的に向き合う必要がある」。2012年、アレクサンドラ・ラングは『Print』誌で、「グラフィック、プロダクト、インタラクションなどのデザイン領域が批評によってはじめて万全で成熟したものになるとすれば、私たちがまだその段階に達していないのは明らかだ」と書いた。そして、2018年に『Fast Company』誌に寄稿したコイ・ビンは次のように述べた。「デザイン業界は一つの産業体として、真に強固なプロのジャーナリストや批評家の層をサポートすることができなかった──ブランドアイデンティティ、デザインシステム、アプリの使い勝手、新製品のデザインといったことのレビューで身を立てるという発想自体がもはやあり得そうもないことになっている」。こういった言説の背後には、デザイナーという職業が重要なものとして受け入れられるためには、それをめぐる批評的な言説が必要だという主張がある。
デザインの実践と批評に関する私のポッドキャスト「Scratching the Surface」でデザイナーと対話をしていると、もっと批評を求めるこの種の意見を何度も耳にした。また、自分の状況が最悪の時期には、私もそう言い続けてきた。私は文章を書くことで、グラフィックデザインに出会った。それまで一度もグラフィックデザイナーに会ったことがなかった郊外のティーンエイジャーにとって、2003年にポイナー、ドレンテル、ビエルート、そしてジェシカ・ヘルファンドの4人が立ち上げたばかりだったブログ「Design Observer」が、デザインの世界への入り口だった。当時、インターネットの普及によって、デザイン関連の言説も新しい波が押し寄せていたのだ。「デザイン・オブザーバー」のほかにも、「Core77」やアーミン・ヴィットとブライオニー・ゴメス=パラシオによる「Under Consideration」などのサイト、また「SpeakUp」「Quipsologies」「FPO」、そして最も有名な「Brand New」のようなブログ帝国が存在していた。ティーンエイジャーだった私は、学校から帰るとすぐに新しい投稿をむさぼるように目を通した。
私が文章を書き始めたのもこの頃だ。しかし、この終わりなきテキストの波にもかかわらず、私はデザインの言説に参加する機会を逃してしまったように感じていた。アイデンティティ・デザインについての深い考察やデザインプロセスの舞台裏を紹介する記事への興奮は、ゆっくりとではあるが薄れていった。紙の雑誌が徐々に衰退する一方で、シーンの先頭に立っていた書き手たちは――いずれにしても批評ではあまりお金にならなかったので――実務に戻っていった。『Emigre』誌は2005年で刊行を止め、『I.D.』誌は2009年に会社をたたんでしまった。昨年[訳注:2019年]には『Print』誌も休刊した(その後、オンライン雑誌として再出発)。さらに、ソーシャルメディアの台頭を受けてデザインブログの勢いも落ちてきた。「SpeakUp」は2009年に閉鎖され、ヴィットとゴメス=パラシオは「Brand New」に専念し、「Design Observer」の投稿は微々たるものになり、他の何十ものデザインブログが休止状態に追い込まれた。
ところが! いま歴史上かつてないほど多くの人びとがグラフィックデザインを話題にしている。1994年、ロックはポイナーにこう答えている。「認識されていないかもしれないが、デザイン批評はどこにでもあり、デザイン教育、歴史、出版、職能集団といった根幹的な活動を支えている」。「たとえば書籍や雑誌の中でデザインされた作品を選び、記述、掲載することも、一つの理論としての仕事だ」。このデザイン批評の定義を受け入れるならば、ロックが考えていたような批評は、実際のところ、どこにでも存在することになる。世界各地には、デザインに関する文章や批評を専門とする大学院コースがある。「99% Invisible」のようなポッドキャストは、つねにトップダウンロードにランクインしている。企業がリブランドすれば、新しいデザインについての議論がTwitterでトレンド入りする(そう、「#DesignTwitter」というハッシュタグがそれだ)。Netflixも『シェフのテーブル』のようなスタイルで著名デザイナーを紹介する番組『アート・オブ・デザイン』でこのゲームに参入した。これ以外にも、深い洞察に満ちた無数のソーシャルメディアのフィード(デザインと政治を結びつけるロックのInstagramアカウント@microcritiqueや、示唆に満ちたデザイン史の宝庫のようなアリス・ローソーンのフィードなど)、あるいは世界各地で創刊されている『Bricks from the Kiln』『Modes of Criticism』『Back Cover』のようなグラフィックデザインに焦点を当てた新しい出版物など、挙げればきりがない。
批評を求める多くの呼びかけの逆説は、それらがデザイン会議で語られたり、学術的なデザインジャーナルに書かれたり、デザイン業界の読者を対象としたデザイン雑誌に掲載されたりすることが多いということだ。なぜデザイン批評が増えないのかという問いは、誤った質問だ。それよりも、なぜグラフィックデザインの周辺でつねに立ち上がる素晴らしい文章を認めないのか、という問いの方が適切ではないか?
批評を求める声は一般的に、「デザイナーのためにデザインについて書くこと」と「一般の人のためにデザインについて書くこと」の2つのグループに分類される。だが、このどちらの声にも、その不可能性が明らかであるがゆえの、ノスタルジックな願望が感じられる。デザインの分野はより大きくより複雑になっていて、さまざまなデザイナーが多様な問題に関心を持っている。こちら側での批評行為の多くは、おもにTwitterやSlackチャンネル、イベント会場などで、より小さなグループによる深い議論の中で行われている。
グラフィックデザインが他のデザイン分野に比べて重く受け止められていない、ということを一般の人びとに向けて説明する例として、建築の批評を挙げるのは分かりやすい。それはグラフィックデザインよりもはるかに長い批評や理論の歴史を持つ分野だ(80年代の『The New York Times』紙にエイダ・ルイーズ・ハックステーブルとポール・ゴールドバーガーという、1人どころか2人もの専任評論家がいた事実を考えてみてほしい)。グラフィックデザインは新しい建物と同じくらい一般の人びとに影響を与えることができるのに、なぜグラフィックデザインの批評家が増えないのだろうか? しかし、出版物の統合や批評家、ジャーナリスト、ライターの解雇が示すように、批評という分野そのものが危機的な状況にある。そして残念なことに、多くの場合、建築評論家は真っ先に切り捨てられるものの一つである。
ハーグ王立美術学院のデザイン講師であるアリス・トウェムローは、「この種の[デザイン批評を求める]言説は、人びとが新聞を最初から最後まで読んだり、世間を代表する共通の見解があり得るとするような、理想化されたロマンティックなメディア環境を前提としている」と語った。「一種の怠惰なノスタルジアだ」。スクール・オブ・ビジュアル・アーツのデザイン批評プログラム(アリスが以前に共同設立し、主任を務めた)の学生を、新聞の批評担当のような仕事に就けるようトレーニングするのは「無駄な骨折り」以外のなにものでもなかった。
批評を求める声が止むことがないのはなぜなのか、ポイナーとの対談から30年近く経った時点でマイケル・ロックに尋ねたところ、彼は表面的なノスタルジアについて指摘した。「こうした声の背景にあるのは、一つの喪失ではないか」とロックは言う。「『これがこそが私たちの批評だ』と言えるような中心を失ったことへのね」。彼はまた、この喪失感は単にメディアを取り巻く環境の変化によるものではなく、グラフィックデザインそのものの性質の変化によるものだと考えている。「私はグラフィックデザインは1920年代に始まり、2008年に死んだものだと思っている」と彼は続けた。「グラフィックデザインはもはや存在しないのだ。なぜならそれがすべてのものに完全に浸透してしまったからだ」。
「グラフィックデザイナー」という言葉は、1923年にウィリアム・アディソン・ドウィギンズが、植字工、印刷工、イラストレーターとしての自分の仕事を表現するために作った言葉だと広く考えられている。マッシモ・ヴィネリが「職能を定義する批評を」と呼びかけたときに考えていたのは、きっとこの言葉のことだったのだろう。しかし、グラフィックデザインは前世紀を通じてより複雑になった。写植や印刷、イラストレーションはもちろんのことウェブサイトやアプリ、インターフェース、ブランド、戦略、ソーシャルメディアなども含まれるようになった。グラフィックデザインはビジネススクールや行政において、枠組み策定の構造や演出手法として捉えられている。マーク・ウィグリーとビアトリス・コロミーナが『我々は 人間 なのか?』で書いているように、「地球全体が地質学的にデザインの層で覆われている」のだ。デザインがすべての文化を貫いているいま、私たちはデザインにどう向き合えばいいのか、つまり、デザインについてどのように話したり書いたりすればいいのか。
ロックとポイナーが『Eye』誌上でデザイン批評について議論するその1年前、デザイナーであり教育者でもあるガナー・スワンソンは、学術ジャーナル『Design Issues』に「一般教養としてのグラフィックデザイン教育(Graphic Design Education as a Liberal Art)」という論文を発表した。この論文の中でスワンソンは、デザイナーの道具は誰にでも手に入りうる、またはそうあるべきものだと提議し、グラフィックデザインは独立した専門分野というよりは誰もが利用可能な一般教養である、と主張している。
「私たちは自分たち自身の修辞学[訳注:グラフィックデザインのこと]を信じ、デザインをコミュニケーション、表現、相互作用、認知を扱う多くの科目の橋渡しをする統合的な分野であると考え始めなければならない。デザインは意味、そして意味が生み出される方法についての、そして形とコミュニケーションの関係についてのものであるべきだ。デザインは科学と文学が出会う領域の一つなのだ。デザインは、社会学や歴史学の隠れた部分に光を当てることができる。民衆の価値観を導き形成するというデザインの立場は、人類学と政治学の間の道でもある。この表現と情報拡散の領域がもたらす視点は、芸術と教育の両者にとっても有益である。デザイナー、デザイン教育者、そしてデザインを学ぶ学生は、私たちが認識している以上に重要で興味深い分野にかかわっているのだ」。
スワンソンの見解は現代においていっそう有効であると考えられる。グラフィックデザインは専門や職業をつなぐ架け橋として、交差領域に存在する職能だ(存在するなら、という話ですよ、ロック)。それは、ほとんどの場合において、それ自身のことではない。グラフィックデザインは文化と商業、あるいはバウハウスのヴァルター・グロピウスの言葉を借りれば、芸術と技術の出会いの場である(スティーブ・ジョブズがアップル社を「テクノロジーとリベラルアーツの交差点」と表現したのは、この言葉を借りたものだ)。ロックはiPhoneが登場したのと同じ2008年をグラフィックデザインの終焉だと位置づけた。それ以前のMacintoshのように、iPhoneは私たちがデザインについて語るときの意味を根本的に変えてしまった。創造、流通、消費のためのツールが、一つのグローバルなデバイスに集約されたのだ。このようなデザインの拡大は、デザインがすべての領域に入り込んでそれを支配する植民地化ではなく、プロからアマチュアへと力を移す民主化をもたらした。いまやデザイナーのツールは、本当に誰にでも手に入るようになった。「私は『デザイン』という区分には、もはやこだわらなくなっています」とトウェムローは言う。「ハーグ王立美術学院で働き始めた頃は、自分をデザインの弁明者のように感じていました。そのように振る舞い続けてきたのですが、そんなにこだわらなくなりました。いまはこの言葉の周りに壁や砦を作らないで、なるようにまかせています」。
ここにグラフィックデザイン批評のパラドックスがある。つまり、実際的に受け止められるためには、グラフィックデザインを他から区別して定義するのではなく、専門の枠組みを超えて扱うことが必要なのだ。トウェムローはヴィネリの批評への呼びかけを読み直したうえで、「あの言い方を読めば、それが基礎を作り、仕組み作り、そして尊敬を得ることについての話だとわかる」と、付け加える。「当時は枠組みを作るための時代でした。デザインとアート、そして、デザインとその他のものとの違いについての枠組みが問題だったのです。しかし、いま私たちはそのような地点をはるかに超えたところにいます」。
2013年の対談から7年が経過したいま、デザイン批評についてどう感じているのか、ロックに尋ねてみた。「不思議なことに、私は楽観的な考えに戻っているよ」と彼は言った。「当時、私が見逃していたのは、デザインがさまざまな分野に広がっていることであり、それに伴って、必ずしもデザインとして認識されていないものについて、大量の批評が書かれていることだ」。たとえばフェイクニュースやフィルターバブル、ミームやSnapchatのフィルター。こういったものごとも、デザインの問題ではないだろうか? ロックは、今日の大衆文化におけるグラフィックデザインの最も明確な例としてミーム――文字どおりテキストと画像からなる――を挙げている。ミームは1990年代に多くのデザイン評論を生み出した議論と同様に、作家性、美学、アイデンティティに関する問題を提起している。しかも、その規模ははるかに大きい。グラフィックデザインが文化的に語られるとき、多くの場合、それはもはやデザインとすら考えられていない。
ヴィクター・パパネックは『生きのびるためのデザイン』の中で、「デザインを孤立化して考えること、あるいは物それ自体とみることは、生の根源的な母体としてのデザインの本質的価値を損なうことである」と書いている。世界がますます視覚的になるにつれ、ビジネス記事やファッション誌、大手新聞やテクノロジー誌にいたるあらゆる媒体で、あらゆる種類の書き手がブランディングやタイポグラフィ、ユーザーインターフェースやスタイルについて普通に書くようになる。デザイン専門出版物もその中の一つだ。トウェムローが語ったように、デザインを新聞の独立したコラムのテーマにしようとする道は、デザイン批評を育むうえでつねに自滅的なものだった。「デザインを難解で深淵なものと見なす態度が、ずっと問題だったのです」。なるほど、グラフィックデザインがどこにでもあるように、グラフィックデザイン批評もどこにでもある。ただ、人びとがデザインを認識すらしないように、それをデザイン批評と認識していないだけなのだろう。
(訳:後藤哲也)
Originally published by AIGA Eye on Design.
Design criticism is everywhere—why are we still looking for it?
ジャレット・フラー (Jarrett Fuller)
デザイナー、ライター、教育者、編集者、ポッドキャスター。ノースカロライナ州立大学グラフィックデザイン学科助教授(2021年8月より)。デザインと編集の複合スタジオ「twenty-six」ディレクター、デザインポッドキャスト「Scratching the Surface」のホスト、そして、「AIGA Eye On Design」の寄稿編集者を務めている。
公開:2021/06/04
 84
84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳
 83
83ワールドワイドウェブのこと/永原康史
 82
82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3
/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81
81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩
 80
80数学と計算機と美学/巴山竜来
 79
79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生
 78
78ひび割れのデザイン史/後藤護
 77
77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史
 76
76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子
 75
75日本語の文字/赤崎正一
 74
74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子
 73
73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部
 72
72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳
 71
71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史
 70
70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子
 69
69作り続けるための仕組みづくり/石川将也
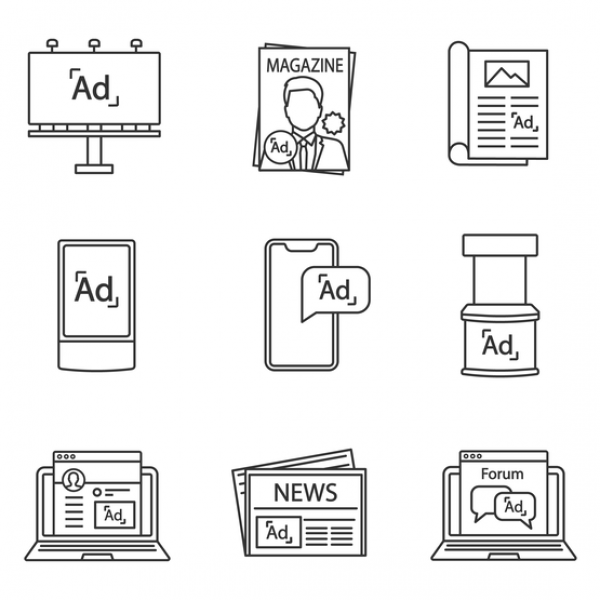 68
68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子
 67
67音楽の空間と色彩/赤崎正一
 66
66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳
 65
65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩
