尾中俊介(Calamari Inc.)
インディペンデントな文化生産実践

九州地方の中心都市、福岡。古くからアジア地域との交流が盛んなこの商業都市は、多くの芸能人・ミュージシャンを輩出するなど、タレント(才能)の輸出地のイメージも強い。最近では創業特区として、官民一体となったビジネスの盛り上がりを見せている。
これらに比べれば、福岡のグラフィックデザインシーンについての認知度は高いとは言えないだろう。九州最大の都市であるため広告業界内で全国的に知られる仕事や会社はあるが、文化生産に関するデザインにおいてはそのかぎりではない。
そんなシーンのなかにおいて、ひとつの杭を打つのがCalamari Inc.尾中俊介の存在だ。福岡を拠点に、全国の美術館やアーティストと協働する彼の活動は、ローカルな活動が注目される昨今のデザイナーの姿を先取りしているようにも見えるが、同時に、つながりや背景が希薄で、時代に逆行した孤高の存在にも映る。
彼の手がけた仕事とそのイメージは全国に流通するものの、尾中自身の経歴については詳しくメディアでは紹介されていない。デザイナーでの活動に加え、出版レーベル「pub」の運営、そして詩人としての顔も持つなど、その活動は多岐にわたる。iTohen鯵坂兼充へのインタビュー(記事No.18)に続き、いわゆる「地方」を拠点としながら、文化生産に関するデザインで評価を得る尾中の、その経歴とインディペンデントな実践について話を聞いた。
Calamari Inc.は、博多駅からほど近いエリアにある一戸建ての2階にある。1階には展示も可能なスペースがあり、後述する尾中の領域横断的な志向が垣間見られる。

尾中は1975年山口県宇部市生まれ。意外なことに福岡出身ではなく、また、美術大学出身でもない。工業高校の機械科出身で、その進学理由は「地元でサッカーが強いから」というもの。宇部という工場地域の土地柄も影響しているという。
工業高校を卒業した後、静岡県のコピー機のトナーをつくる工場に就職しました。ただ、絵や工作などのモノづくりが子供の頃から得意だったこともあって、自らの手でなにかをつくる仕事に就きたいという気持ちが漠然とありました。その頃から『Studio Voice』や『Cut』などの雑誌を読みはじめるようになり、そ
こに載っていたデザイン専門学校の広告を見て、仕事を辞め学校へ 行くことに決めました。その頃は長谷川集平さんの絵本や『絵本づくりサブミッション』という本に影響を受け絵本作家を目指そうと考えはじめたときだったので、イラストレーションを学ぶつもりでした。
そこから福岡の専門学校に進学したが、なぜ東京でなく福岡だったのだろうか。
はじめは東京の学校へと思っていたのですが、金銭面から新聞奨学金制度を選択し、引っ越し費用も考
慮して実家から比較的近い福岡の専門学校を選びました。そしてそのまま福岡にいます。結局イラストはあまり上達せず、絵本作家になる目標は徐々に薄れていき、卒業後は成り行きで福岡のデザイン事務所に入っていました。1998年のことです。
グラフィックデザインへの関心は、事務所に入ってから生まれたという。そのきっかけは、当時の多くの若者同様、音楽を入り口にしたものだった。
グラフィックデザインに興味を持ったのはデザイン事務所に入ってからですが、事務所の仕事によってではなく、インターネットや雑誌によって外の世界を知ったことがきっかけでした。就職した事務所は商業的な広告デザインがおもな仕事で、消費を促すことに主眼が置かれた仕事は自分の性には合わないことがすぐにわかりました。
グラフィックデザインへの入り口は音楽でした。ニルヴァーナやフガジ、ソニックユース経由でノイズやポストロックといったインディーズの音楽シーンを知り、ゼロックスコピーとコラージュの手法でつくられるチープでダーティなファンジンやジャケットデザインに触れたり、デヴィッド・カーソンのデザインした雑誌『Raygun』のドレスダウンしたタイポグラフィに魅せられていました。とくにTomatoは、音楽、写真、文学などの分野を横断し、モホリ=ナギらバウハウス的モダニズムを意識させつつもあくまでアクチュアルな実践として活動していてとても刺激的でした。
Tomatoやデヴィッド・カーソンが掲載されているという理由で購入した僕にとって初めての『アイデア』は「抽象表現の現在」の特集号でした。ここで矢萩喜従郎氏や大竹伸朗氏のことを知り、ヨゼフ・ミューラー゠ブロックマンらスイス・スタイルに出会いました。ミニマリズムや抽象表現主義などの美術的動向にも目を向けるきっかけとなり、この特集によって僕のその後のグラフィックデザインに関する問題意識のいくつかが芽生えたのだと思います
そして、デザイン業界の環境がコンピューターへの移行期であったことが、尾中が自分自身の制作活動を追求することを後押しした。
ちょうどこのタイミングで、頑張れば買えるくらいに安くなったPower Macintosh G3が登場したので、借金をしてそれを購入し事務所も辞めました。もしもの話をしても意味をなさないですが、もし写植の時代やそれ以前にグラフィックデザイナーを目指していたかと問われれば、そうではなかったと答えます。僕は怠惰な人間なので、Macでひとり自由に制作できる環境を得たことがグラフィックデザイナーを目指すきっかけのひとつだったと思います。
この頃尾中は、福岡のインディペンデントなアート活動のひとつの重要な拠点であるart space tetraの立ち上げにも加わっている。いわゆるデザイナーの活動の枠を超えたこの領域横断的な行為が、結果的に尾中のデザイン活動につながっていく。
「art space tetra」は、キュレーターの遠藤水城氏とアーティストの安部貴住氏が発起人となり、2004年福岡市博多区に設立されました。1998〜99年頃、僕は友人とともにグラフィックデ
ザインだけでまったく情報のないフリーペーパーを制作 し配布しはじめたのですが、遠藤氏とはこのフリーペーパーがきっかけとなり知り合いました。
その頃の彼はまだ大学院生で、自身の小さな雑誌を刊行しはじめたばかりでした。その雑誌の企画としてインタビューさせて欲しいと声をかけられました。
その後、彼や友人たちと電子音楽や実験音楽、即興音楽などのイベントを立ち上げたり、遠藤氏が企画した展示や講演会のチラシをデザインしたりしました。
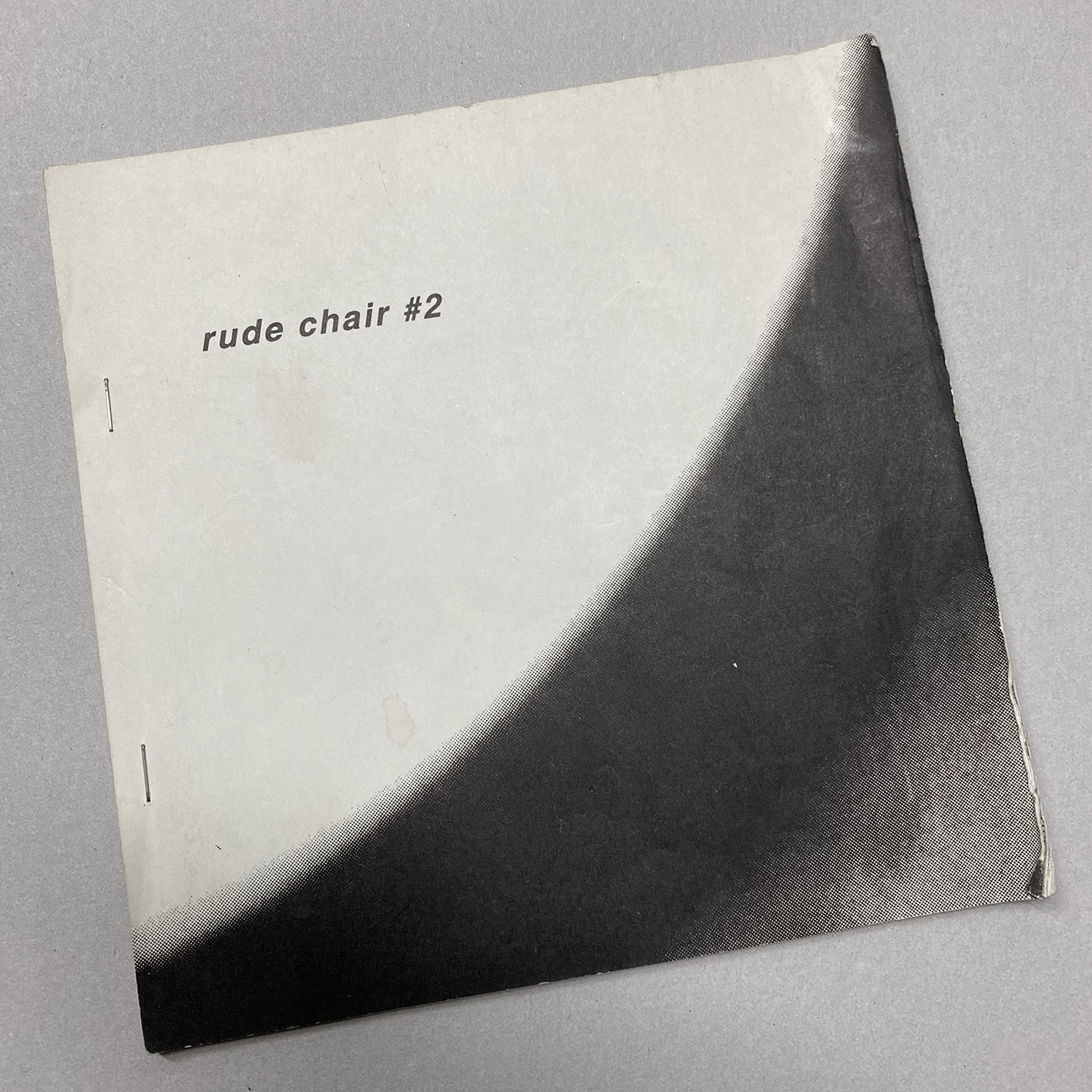
この流れで場所を持つ話になり、オルタナティブスペースの開設へと向かいます。賛同する美術家や音楽家、デザイナーらとともに共同運営するという形をとっていました。
tetraではそれぞれが企画した展示やイベントにつ
いて感想や批評や意見をぶつけ合い、随分と刺激を受けました。大学へ進学しなかった僕にとってtetraは大学のような場所で、非常に青臭く深い学びがありました。
僕はその建物の屋根裏部屋でデザイン事務所をはじめました。当然デザイン仕事の依頼はないのでバイトをしながら、自分たちで企画した展示や音楽イベントのチラシをデザインし、印刷していました。そしてそれらをファイリングして美術館や文化施設に届けましたが、実際に依頼が来るのはそれから2、3年も経ってのことです。そして同じくtetraのメンバーだった田中慶二氏とともにデザイン事務所「Calamari Inc.」をつくり現在に至ります。
遠藤氏との仕事でいえば『アメリカまで』『曽根裕|Perfect Moment』『陸の果て、自己への配慮』という彼の編著による三つの書籍のデザイン・組版に関わっています。この三部作は、紙が黄ばんだり、破れていたり、インキが擦れて紙地が見えたりと、紙というメディウムの脆く儚い特質を露わにした仕様に
しています。これは書籍を不変的な物としてではなく、朽ちていく 過程という時間が内在してあることを示すための、遠藤氏のキュレ ーションを踏まえた方法でした。
(編注:尾中氏や設立メンバーがtetraの運営に関わったのは2012年まで。その後は新しいメンバーによって運営されている。)


Photo: Shintaro Yamanaka (Qsyum!)
一度は上京を考えた尾中だが、独立の際にふたたび福岡を選んだのはなぜだろうか。「福岡のデザイン(コミュニティ)」をどのように見ているのだろうか。
福岡に強いこだわりがあるわけではないです。若い時には新宿私塾でタイポグラフィを学びたくて東京に行こうかと考えたこともありましたが、出て行かなかったのは福岡の街のサイズが自分に合っていて住み心地がよかったからなのだと思います(あと、やはり怠惰…)。
福岡のデザインコミュニティについては、あるのかどうかも知らないくらい関わりがないので、福岡を代表するかのような発言はできません。才能ある若いデザイナーがいることは知っています。た
だ、どの団体にも所属しておらず、同業者に認知もされていないの で集まりに声がかかることもありません。
福岡は商業というか経済の比重が大きな街で、街の規模に対して文化的な施設やイベント、展覧会の企画は少ないというのが僕の印象です。ですので外に仕事を求めるのは必然的な選択ですし、ありがたいことに県外からの仕事の依頼の方が若干多いです。とはいえ、近くの美術館で奮闘している学芸員さんや小さなギャラリーのオーナーの方々との仕事は、やはりコミュニケーションがスムーズで仔細な意図も汲みやすく、展覧会の企画段階から参加させてもらえるので、ともに戦っている同志の感覚が強いです。
地方にいることのメリットでいえば、メインストリームでは当たり前とされるような価値観から遠く離れることができる、ということはいえるかもしれません。遅いデザインや弱いデザイン、遠いデザインや分かりにくいデザイン、貧しいデザイン、不合理なデザインということを考え、実践することができ
る。しかし地方といえど福岡も都市ですし、これはどちらかといえ ば僕個人の特性であり、資本主義社会、消費社会へのカウンターと して行っていることだと思います。それ自体が目的ではありませんが、正解からこぼれ落ちていくものたちとともにあろうとすることは、プロセスのなかで自らの立ち位置を勘違いしないように律するためにも、つねに意識していることです。
地方都市で文化生産に関するデザインだけで生計を立てることは容易ではない。領域横断的に活動するデザイナーが地方に多いのは、経済的な理由もあるだろう。しかし尾中には、文化芸術に関する仕事に強いこだわりがある。
展覧会グラフィックが面白い理由に、ひとつのプロジェクトで広報用のポスター、チラシ、会場のキャプションや看板サイン類、そして記録としての図録(カタログ)のデザインに関わることができるという点があります。つまり、展覧会というメインのイベントとそれ以前(広報印刷物)、それ以後(カタログ)。
たとえば、1970年の第10回日本国際美術展(東京ビエンナーレ)「人間と物質」展の〈カタログ〉のように、展覧会の記録ではなく、展覧会前に事前に依頼して経歴に1ページ、展示のプランに1ページ、自由なレイアウトができる1ページの計3ページが各作家に割り
当てられるという面白いアプローチのものもありました。(展示を 記録した冊子は〈作品集〉として展示後に編集されている)
このようにひとつの展覧会というプロジェクトの全体を多角的に捉えることができる位置に立てるのが、グラフィックデザイナーであること。この特殊なあり方は、とても面白い経験や新たな発見をいくつももたらしてくれます。また、紙のポスターと本を、いまこの時代に制作できるということも大きいです。
美術だけにこだわっているわけではないので、映画、音楽、建築、演劇、文芸など芸術全般のグラフィックにもいま以上に関わっていきたいと考えています。


尾中は出版レーベル「pub」を立ち上げ、これまでに3冊の出版物を刊行している。セルフパブリッシングは、文化生産に携わるデザイナーの今日的な活動として定着しているが、詩人としての活動も行う彼の詩集は別の方法で出版されている。出版活動の狙いはどこにあるのだろうか。
pubという出版レーベルは、マーケティングや傾向対策などのリサーチによらず、ただ自分たちが興味を持った内容を見つけ、それによって導き出される造本形式のヴァリエーションのうち、僕たちがもっとも実験的と思える一形態を出現させる試みとしてはじめました。
僕が発行者であり企画と編集・デザインを担当し、Calamari Inc.の田中がプロデューサー兼Webデザインを担当しています。
これは少しでも自由度をもって本をデザインするためのプロジェクトで、まずは作家とアイデアを共有するまでのプロセスを楽しめるかどうか、また売れることよりも実験として面白いかどうかに重点が置かれています。
一冊目は遠藤水城氏の『陸の果て、自己への配慮』です。


Photo: Shintaro Yamanaka (Qsyum!)
竜飛岬を出発し、震災の爪痕が残る2012年の真冬の東北の沿岸をひたすら徒歩で南下した遠藤氏が、メモ帳に綴った63日間の記録です。
ジャケットには津波の被害が甚大であった宮城県名取市
沿岸の車道で僕がスナップした擦れた白い外側線の写真を使用。この写真を2版で分解し、黒の色上質紙にUVの白インキで版それぞれを2度、3度の計5度も刷り重ねたものです。つまりタイトルや著者名などの文字やISBNのバーコードなどは、インキが抜かれた紙地の黒で表現されているということです。
ほかにも表紙にNTスフールというヌメっとした独特の触感をもつ用紙を採用したり、本文の前半と後半で文字サイズや行数などの設計を変え、とくに後半はメモ帳における改行や誤表記を再現するよう組版するなど、遠藤氏のメモの言葉と照応するようなデザインを心がけて造本しました。
二冊目は彫刻家、近藤祐史氏のセメントを媒体とした自刻像を収めた作品集『YUJI KONDO|SELF PORTRAITS』です。


Photo: Shintaro Yamanaka (Qsyum!)
近藤氏が平安・鎌倉の仏像彫刻に影響を受けているということを知ってデザインした特殊な背表紙は、顔が縦に裂け内側から十一面観音が現れる「宝誌和尚立像」から着想しました。
一枚の紙を折りたたむフランス装をアレンジして設計しています。あらかじめ印刷・トムソン抜きしたものを近藤氏と僕とで手作業で折り、その後製本職人に表紙貼りしてもらっています。
図版撮影は近藤氏のアトリエにて、深夜に微量の光源のみを用いて写真家の原田要介さんに撮影してもらいました。暗さのなかに自刻像が浮かび上がるという、近藤氏が展示でも行っている霊的な演出の雰囲気に近づけています。
三冊目は彫刻家・国松希根太氏の初作品集『KINETA KUNIMATSU|HORIZONTAL DEPTH』。


Photo: Shintaro Yamanaka (Qsyum!)
北海道白老町飛生のアトリエを訪ねた時の風景や作品の印象から、糸縢りにした本文を寒冷紗でくるみ綴じし、厚さ3.5mmのチップボールの板紙で挟むドイツ装に近い形を採用して、モノとしての存在感を強調させています。
また、国松氏の作品に象徴的な「水平線(HORIZON)」を、建築現場で地墨を引くための墨壺に白のインキ塗料を入れて彫刻家の手作業によって引いてもらいました。このとき本を数冊横並びにして引くためラインの表情が一冊ずつ微妙に異なる表紙となります。タイトルも一冊一冊スタンプで押しています。
本文のページ構成については、テキストページが図版ページをいくつかまたぐようにレイアウトしました。これは連続性を分断し、読むというリニアな時間に変化を与え、厚み(深みDEPTH)を意識させるようにできればと考え採用しました。
まだ三冊に過ぎませんが、実験的なものを制作・出版することを心がけています。これからの出版企画もいくつかありますし、私の活動のなかで手付かずになっている流通についても考えはじめなくてはと思っています。
これまでも中央から離れた場所で自らのペースで活動を行ってきた尾中だが、コロナ禍でさらに距離の空いたいま、これからの活動についてどのように考えているのだろうか。
コロナ禍だけを問題としているわけではないのですが、モノをつくる立場としてなにをどのような形で後世に残せばいいのか考えているところです。
リモートやSNS上だけで人と接しているとその仲間内だけが世界のように感じたり、外からの別の意見に対していちいち過度に反応してしまったりと、空間的にも時間的にもとても狭い範囲で物事をはかってしまっていることにがっかりしています。もっと遠い過去や遠くの人、遠い未来に思いを馳せてモノを考えつくっていかなければと。
またそのような遠望とは別のベクトルとして、4年ほど
前から妻に誘われて田畑に立っているのですが、土に触れることで あらためて足下に目を向け、デザインという仕事はもちろん生活に関し ても見つめ直そうと思っています。
それと今年こそ詩集をまとめたいですね。
後藤哲也(ごとう・てつや)
デザイナー/キュレーター/エディター。福岡出身大阪在住。近畿大学文芸学部准教授/大阪芸術大学デザイン学科客員教授。著書に『アイデア別冊 Yellow Pages』、最近の展覧会企画に「GRAPHIC WEST9: Sulki & Min」(京都dddギャラリー)などがある。
公開:2021/03/22
 84
84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳
 83
83ワールドワイドウェブのこと/永原康史
 82
82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3
/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81
81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩
 80
80数学と計算機と美学/巴山竜来
 79
79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生
 78
78ひび割れのデザイン史/後藤護
 77
77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史
 76
76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子
 75
75日本語の文字/赤崎正一
 74
74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子
 73
73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部
 72
72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳
 71
71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史
 70
70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子
 69
69作り続けるための仕組みづくり/石川将也
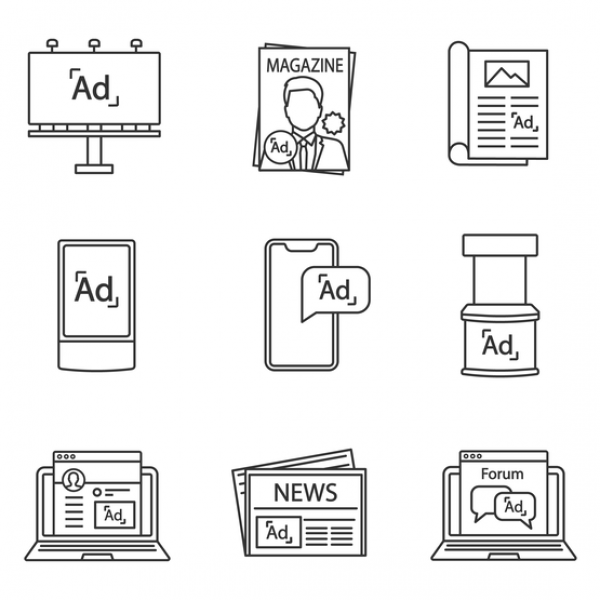 68
68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子
 67
67音楽の空間と色彩/赤崎正一
 66
66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳
 65
65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩
