出来事としての「詩」と「デザイン」

デザインの世界ではコンテンツになにがしかのフォームを与える、という図式で考えるのが一般的だ。しかし、具体的なかたちを伴わない無形の思念のようなコンテンツは存在しない。コンテンツはなにがしかのフォームとともにひとつの出来事として同時に現れ出るものではないだろうか。詩書は、そのことがもっとも先鋭的に示されてきた領域だ。90年代からテクストと造本が一体となった作品を制作し、 近年もユニークな詩誌『アンパサンド』で注目を集める著者が、自身に影響を与えてきた「出来事」としての詩書を紹介する。
(撮影:Northern Studio 大島拓也)
「詩」と「デザイン」といえば、日本ではまず、近現代の文芸史に連なる詩集が思い浮かぶだろう。現在でも「美しい本」という名のもとに語られる書物には詩書が数多い。出版の近代化、本の量産化が進んだ20世紀初頭、早くもそれに抗うようにして、大正初期の近代詩と詩書の歴史がはじまる。昭和初期までの西洋の書物を範とする豪華な美装本に続いてモダニズム詩の時代がはじまり、前衛美術を採り入れながら、詩は一挙にデザインに接近していく。
いきなり話の腰を折るようだが、私はこのような近現代詩書の展開について知らないまま、予期せぬ巡り合わせからテクスト作品を本の形式で発表しはじめ(空中線書局、未生響名義、1994~)、自分なりの「詩」と「デザイン」への関心から、自主制作作品集の編集・制作を行う仕事を続けてきた(アトリエ空中線、1999~)。
振り返れば、異常にコトバに惹かれているのに何か言いたいことがあるわけでなく、「詩」といわれる領域についてはその人間臭が厭わしく思われた。「詩」にも「デザイン」にも予感ばかりを抱きながら、揺動しているといったふうだったのだ。
そのうち、幾人かとの幸運な出会いから60、70年代の詩・美術系小出版社の本が掌にのることになったり、ページの中にまるで作家が媒体となって享(う)けたものでもあるかのような未知のコトバを見つけて狂喜したり、欧米にコトバと美術をとりなす小プレスが多く存在することを知ったりすることとなった。日本の近現代の詩書とプレスについても遅ればせながら学んだ。
そうして徐々に目にする「詩」と美術の本は、なんと多様かつ自在であったことか。なににつけ、知らないということは時によいもので、ピンとくるものを手にして、なぜこれがいいのか、自分が何にトキめいているかを考えてみることができる。
こういった思索を繰り返してきて、最近になってようやく一つの大きな要素が浮かび上がってきた。「出来事」である。企画や編集途上の、また制作途上の「出来事」。「出来事」から生まれる「デザイン」、「出来事」を生む「デザイン」。小稿ではそのような「出来事」としての詩書を思いつくままに紹介してみたい。
◉『草子』1-8号

初期・書肆山田の叢書『草子』。シリーズの企画・形態の発案者は、第1号を飾る瀧口修造。各巻はアンカット16ページの折丁にタイトルの色紙を一枚巻いた体裁。この16ページに一篇の詩が収められており、シリーズが完結したときに、読者が望めば折丁をまとめて1冊に合本し好きなように製本装幀することができる、という趣向だった。各冊のページの上部には、合本する際に必要となるノンブルが通しで印字されている。
読者は一冊で一篇の詩に相対する贅沢を経験し、ある者は合本・装幀する愉しみを味わう。各巻の詩人にとってもこれは一つの出来事であったに違いない。16ページは雑誌に寄稿する一篇に比べると広く、それぞれに方法を講じて一冊を完結させている。
初めて手にしたのは岩成達也+風倉匠『レッスン・プログラム』。背もなく薄い冊子にただ一篇という形式が潔く、厚い表紙もなく素裸の言葉を見るようだった。これだ、と直感して、折しも用意していた自分の第一作品を(頁数は違えど)『草子』に倣って作った。
◉加納光於『《稲妻捕り》Elements』/瀧口修造『《稲妻捕り》とともに』

書肆山田、1978年
通称『稲妻捕り』。この本こそ、二人の作家が作品を出来事にして本に封じ込めたかのような一冊。加納光於が1977年に石版画の連作として制作した「稲妻捕り」の一部(No.3収録)と、「その制作過程に呼応して書かれた」瀧口修造の手稿が収められ、カラー刷りの画(マット紙)とペンの走り書き(レイド紙)が一枚ずつ120ページにわたって交互に綴じられている。
もとより、色の混合やエフェクトを考えた色彩設計と偶然から、作品そのものが出来事でなければ本当でない、といった作法を徹底する画家が、鬼気迫る筆の動きで次々と稲妻雲を出現させる。
紙に定着したそれらを見ながら、意識に飛来するものを瀧口が書きつける。作品についてのメモもあれば、詩的フラグメントも多い。消したり書いたりしたものがそのまま本に印刷され、意識を生け捕ろうとする瀧口の書き取りを生け捕るという、出来事を写し取ったかのようなページだ。
何度開いてもどきどきする。そして、こんな画が、こんなフレーズがあっただろうかと思う。
ブックケースには、加納光於による「稲妻捕り」の制作プラン。大枠のフォルムと色の配合がこと細かに書き込まれたもの。制作プロセスという出来事こそが作品に表象されると考えるだろう画家が装幀すると、こんなデザインになる。
◉山中散生(編訳)『コレクション・オパール』/佐々木桔梗(編)『コレクション・サフィールⅠ、Ⅱ』

佐々木桔梗(編)『コレクション・サフィールⅠ、Ⅱ』プレス・ビブリオマーヌ、1965-66年
こちらも、日本の美術界が躍動していた60~70年代を中心に、詩と美術と書物を愛した屈指のインディペンデント・プレス。ありとあらゆる形の本が作られたが、ここに挙げたものが一番に出来事を想起させる。いわゆる友の会式で、定期的にこのような二つ折りの印刷物が郵便で届く。
『コレクション・オパール』は、山中散生が海外のシュルレアリスム周辺作家の画と詩または文を組み合わせたシリーズで、全20点頒布。各限定175部ながら、多くが別売りの専用夫婦函に入った状態で現存している。『コレクション・サフィール』は佐々木桔梗の発行・編集による日本の作家も交えた詩画集で、第1輯、第2輯あわせて計33種。
図中で立っているカードは、野中ユリのコラージュにマルセル・シュオブの文。文字は上品な紫のインキで活版印刷してあり、あるいは野中さんの要望であったかもしれないと察してみたり、裏にあるシュオブの『架空の伝記』とこのコラージュが結びついた経緯のメモ書きに頷いたり。ひと組ごとに並ならぬ思い入れの編集が出来事として薫りたち、函の中の宝物になる。
◉エディツィオーニ・プルチノエレファンテの本

こちらはイタリアのインディペンデント・プレス「エディツィオーニ・プルチノエレファンテ(EDIZIONI PULCINOELEFANTE)」の本。一人の詩人の一篇の詩に一人の美術家が作品を制作して8~12ページ程度の詩画本とするスタイルで、企画から活字組版・印刷・手彩色・配本まで、実に一人によって行われている。1タイトルあたりの発行部数が30部程度と極端に少ないが、手彩色までを一人の手で行うにはこの部数が限度ということだろう。
挿画は、絵、版画、写真、物体など、ほとんどのものが許容され、作品の大きさによって判型も決まる。着彩ガラスのカケラが貼り付けてあるものもあれば、線画に赤い糸がページを越えて縫い通してあるものもある。現時点で一万タイトルを越えるという膨大な書目は驚異的であり、それほど読者に求められ続けているのは、主宰が詩人と美術家を一冊ごとに引き合わせて作る=出来事が魅力に満ちたものであるからに他ならない。
作家が作家を呼び、アイデアがアイデアを広げ出来事を生み、本に定着する仕組みがエディツィオーニ・プルチノエレファンテの本だ、ということもできるだろう。
◉Anne & Mario Daniele『La mappa dell’estasi』/Lidia Kuscar『A Quick Tea』


Morgana Edizioni、2000年
同じくイタリアより、1985年からフィレンツェで美術・文学を中心とした書籍を制作・刊行する「モルガナ・エディツィオーニ(Morgana Edizioni)」。ここは小さなギャラリー「Minimum」も併設する出版社で、個々の展覧会に合わせて記念品のような小箱本を制作していた。これもまたギャラリーが選んだ詩人による言葉と作品を一緒に収めるという形式で、テクストと美術が照応する出来事を生み出していた。
小箱本は各30部ずつで、展示作家はそのために作品を30点制作しなければならない。それだけでも充分な出来事だが、私が目に止めたこのテラコッタ作家は全部違う形のものを作ったそうで、それらだけでも展覧会ができそうなひと仕事だっただろう。おかげで、私も残っているいくつかから選ぶ愉しみをもらった。
◉未生響『Bone-Bone O’clock』

空中線書局、1995年
拙作(未生響名義)のテクスト+造本作品より、いくつかの体験を。同音・類音の遊戯で制作した第二作品の出来事は、初心印刷と初期DTP。この頃まで印刷の仕組みをよく知らず、黒い紙に銀ホイルの線と濃いピンクの星を刷りたいと所望したところ、シルクスクリーン印刷と銀箔押しという、今なら考えにくい表紙に。
本文は、真夜中に昼間の用から解放されたコトバが頭蓋のサーカステントに躍り出し戯言する映像を反映すべく、アコーディオン製本をタテにスクロールしながら銀の文字を追う形とし、オフセット印刷。
DTP初期で版下も混沌。表紙はテクスト、図形ともに写植。本文はAldus Page Makerで組むもデータとして入稿できず、プリントアウトしたものを版下に使うことになるが、そのザラつきもそれはそれでと思われた。結果、色々のテクスチャーが混合した妙な本になった。
◉未生響『Muse-in-the-Slot』

空中線書局、1996年
語をつなげず並べて置くことで、語同士の照応をうかがう往古のプロテウス詩に倣い、語をシャッフルして並べ、それを三つ組みにしたり、短い文にしたりの実験を試みた作品。
ブックレットとともに、読者各々が無関係な語の結合による奇妙な映像を味わえるようにと、三つずつ語を並べた塩ビの小さなカード30枚入り小箱を付録した。3語のカード30枚でかなり多くの組み合わせパターンが発生する。当時は意識的ではなかったが、今ではそれが読者の出来事になったかもしれないと思う。
◉未生響『Skhola Kairos』

空中線書局、2015年
第一作品『ファザーランド・ジャンボリー』とその関係のテクストを集め、絵と戯文が一つになったような一幅の光景にした、「ポエオラマ」と名付けた形式の作品。
それまでの脱主体のためのさまざまな言語遊戯と同様の感覚で、思い浮かぶモチーフを大まかに線描し、作品の中から長さが近い文を置いていく。長さが足りなければ別のところから取ってきて付けてもよく、より逸脱を促す方向であればノートの走り書きから持ってきてもいい。いわばパズル式の遊びとして有効だった。
思えば、主体的な表現から逃走してきた分、最初から出来事を介入させるための遊戯やルールや方法を用いて言語に美術をさせることが、自分には重要だったように思う。表紙は「ファザーランド」のマークである「AEIOU TAIYOO」と「A」「E」「I」「O」「U」の文字だけで作った風景。
◉山本じん(画)、未生響(文)『NATURA』

造本:アトリエ空中線
ギャラリー・ロイユ、2018年
美術制作そのものから出来事の発現を念じて取り組んだ事例を一つ。山本じん氏の新作銀筆画展が企画された折、画集を制作したいのでそのテクストを書かないかとの話を受けた。通常のように絵に言葉をつけるという説明的な方法はとりたくない。互いに思考を引っ張られることなく制作して、後で突き合わせてみようと。氏は「根源的な自然」が描きたいと言い、タイトルだけ『NATURA』と決めた。
完成披露会では互いの作品の意想外と符号の混合に驚き、両者を引き合わせることで自らの作品に新しい切子面が感じられた。便宜上12の画それぞれに呼応の面白い12のテクストを合わせたが、読者がシートをどのように入れ替えて見てもいいように、綴じない状態で収めた。
◉未生響『NATURA テクスト特装版』

空中線書局、2018年
『NATURA』の展示では、羊皮紙に銀筆といった天然材料ばかりの画の隣りに、四角い紙パネルを貼ることははばかられ、自然の石である雲母板にシルクスクリーン刷りを試みることにした。電子製品の小さな絶縁体となる雲母板は、産地から専門の商社を通して卸されているのみで、いくつか問い合わせ、ようやく掌ほどの大きさがある雲母板を少しまとめて入手できた。断裁はせず、最大のかたちで剥離されたそのままの形状で使用した。
ところが、印刷所でテストしてもらうと、シルクスクリーンではインキが鉱石に定着せず刷れないことがわかった。この時は知識が役に立った。インクジェット式でガラスや石にも瞬時にインキを定着できるUV印刷がある。無事、雲母板に白い文字を印字し、壁から少し浮かせて固定する脱着可能な金具を作って展示することができた。そして、同様の方法で扉や奥付も刷ってアクリルケースに収め特装版とした。限定4部。入手できた雲母板の枚数から部数が決まった。この特装本とデザインは、思いがけずほとんど出来事が作った、と思うと不思議。
◉アトリエ空中線(編)『アンパサンド』

編集・造本:アトリエ空中線
灯光舎、2020-22年
最後に、コンテンツにもデザインにも出来事を期待する積極的な方法として企画した、現在進行中の媒体を。2020年、京都・灯光舎の設立と同時に共同企画(灯光舎×空中線書局)として創刊した雑誌『アンパサンド』。
1テーマで6号展開、終了すれば次のテーマと編集者・執筆者に制作が移行するというスタイルをとる。『アンパサンド』[「&」記号]というタイトルは、多ジャンルの作家・作品が一つのテーマを通じて集まり、共鳴と拡がりを生むような場を志して命名。個々の作品はそれぞれの内容にふさわしい形態に仕立て、一つの封筒に収めるスタイルとした。
第Ⅰ集のテーマは「詩的なるものへ」(「詩=抒情詩」から、「詩的」であるとはどういうことか、への転換)。7人の作家によって6回の連載作品が用意され、たとえばBOOKSOUNDSによる手紙小説は便箋と封筒。川添洋司による写真と詩的フラグメントを組み合わせた作品は、立てて味わうこともできる二つ折りカード。
庄司太一の瓶とポエジーについてのエッセイは、旅のポケットによいチャップブック。福田尚代の回文作品は、のりしろの付いたアコーディオン・ブックレットで、連載完結時に第一回の表紙と最終回の裏表紙を貼りあわせることで1冊の回文集ができる仕立て。
私自身が寄稿するエッセイも、各回が16ページの折丁になっており、6回分をまとめて製本・装幀すれば『PHILOPOESIS I 詩的なるもの――20世紀美術家たちの言葉』という本になる仕組み。このあたりのアイデアは、最初に取り上げた書肆山田の『草子』シリーズに負っている。

大森由美子のテーマごとのワークブック。大森は作品制作とともに制作ノートを書いて発表し、撮影、グラフィックデザインも自らの手で行う。したがって、氏の作品については発表形態をすべて任せるのが最善だった。通常の冊子の場合もあれば、写真やコラージュをレイアウトした折ブックレット、写真に写された実際のひまわりの種が一粒ずつ封じ込められたこともあった。

写真家・村松桂によって本誌のために考案された「レイヤースコープ」。1号で用意された白い台紙の上に、2号から封入される透明シートを重ねていき6号で完成する。毎号2種類のシートが用意されており、どちらを選ぶかで言葉と写真の完成パターンは32種となる。読者の手元で作品がオプティカルかつポリセミックな拡がりを発揮する。おそらく作者自身も制作途上でこの出来事を愉しんだことだろう。
『アンパサンド』第Ⅰ期完結のあかつきには記念展が予定されており、各号を独自の体裁で一冊にまとめたものを提示してみたいと考えている。
* * *
私が自身でレーベルを始めたのは、既存の格好よくも美しくもない自費出版サービスよりは、低予算でも自分の思い通りのものを作るほうが余程いいという考えからだった。自主出版であれば流通に伴う制約に囚われることもなく、内容にふさわしい本が実現できると考えた。
当初私は、作品から編集、判型や書容の動機を探ることを第一義とし、作品の特質を映し出すためには物質性にこだわるべきだと思ってきた。だが、振り返ってみれば作家とディスカッションしながら進める過程で、内容かデザインに一つでも想定以上のプラスワンが生まれるように意識をひらいておくことが、今回いうところの「出来事」を生み出していた。
「詩」も「デザイン」も一般的には主体的に統御されるもの、つまり「詩」は作者の内面的な表現であり、「デザイン」はとくにデジタルツールが主流になってからは、フラットな枠組みと論理に収められるものと思われている。
しかし、ここに紹介した数々の詩書は両者が本質的には「出来事」であることを教えてくれる。「詩」は日常の規範を超えた「コトバ」=「セカイ」との出会いであり、「デザイン」もまた機能という論理を超えた詩的な出来事へと開かれている。
間奈美子(はざま・なみこ)
言語美術、エディトリアル・デザイン。1994年、未生響名義で自身の詩的テクストと造本を一つとした作品を刊行するインディペンデント・プレス「空中線書局」を開設。刊本、展覧会多数。1999年、主に作家・ギャラリーより、文学・芸術を中心とした作品集・書籍の編集、造本・制作までを請負う「アトリエ空中線」を設立。2015年~22年、京都芸術大学講師。2022年10月、新刊『復刻版/録音盤 ファザーランド・ジャンボリー』(未生響 × NOISECONCREATx3CHI5、空中線書局)が刊行予定。動画「アトリエ空中線の仕事——インディペンデント・プレスの展開 1999-2022-』(企画制作:Northern Studio、アトリエ空中線)近日公開。
Twitter: @biblio_kuchusen
Instagram: kuchusenshokyoku
公開:2022/09/29
 84
84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳
 83
83ワールドワイドウェブのこと/永原康史
 82
82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3
/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81
81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩
 80
80数学と計算機と美学/巴山竜来
 79
79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生
 78
78ひび割れのデザイン史/後藤護
 77
77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史
 76
76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子
 75
75日本語の文字/赤崎正一
 74
74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子
 73
73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部
 72
72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳
 71
71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史
 70
70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子
 69
69作り続けるための仕組みづくり/石川将也
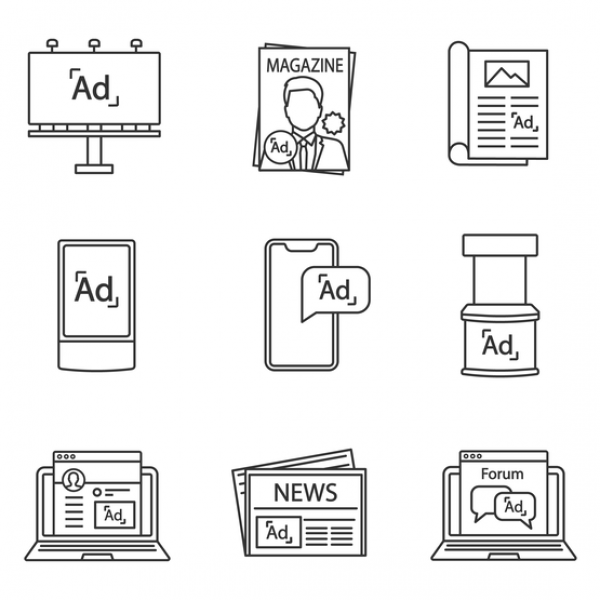 68
68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子
 67
67音楽の空間と色彩/赤崎正一
 66
66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳
 65
65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩
