ビデオのデザインに憧れて

1970年代半ばの登場以来、20世紀末の社会や文化に大きな影響を与えた家庭用ビデオテープデッキは、世紀の変わり目を境にしてデジタル動画技術の発展とともに衰退していった。しかし、80年代から90年代にかけて大量にリリースされたビデオには今では流通していない貴重な作品が数多く残されているほか、そのパッケージや広告にも独特の味わいがある。ビデオテープメディアに魅せられたデザイナーが語る、ビデオパッケージデザインの豊かさ。
2013年頃から数年間、少なくとも日米の一部の映画ファンのあいだでは、ビデオを回顧する動きが盛り上がった。ホームビデオの歴史や意義を振り返るドキュメンタリー映画『Rewind This!』(2013年、アメリカ)の存在を知ったときには、わたしもすでにビデオの魅力に取り憑かれており、翌年『VHSテープを巻き戻せ!』という邦題でこの作品が公開されるタイミングで自主雑誌『南海』を創刊し、「VHSの現在(いま)」という特集を組んだりした。
日本ビデオ協会が公式にレンタルシステムをスタートさせたのが1983年。ここからレンタルビデオの大ブームが始まる。わたしが生まれたのはその翌年だ。幼い頃住んでいた家の近所にもレンタルビデオ店があり、週末になるとかならず親に連れられて行った。まだ映画館すら知らなかったこの時期に、先にビデオを体験してしまったのだ。こうして映画というものはわたしの人生に、時代や評価に関係なく、パッケージされて平等に並んでいるものとして入ってきた。
レンタルするのはもっぱらゴジラ映画。本編にはない、つまりスチール写真用に演出された、怪獣たちが勢揃いした写真が使われている『怪獣総進撃』(1968年。昭和のゴジラシリーズ末期の一作)のビデオが本当に好きだった。何度も繰り返し借りたし、そうでなくても、店に行くたびにじっくりと眺めた。また、家から離れた別のレンタルビデオ店に連れられて行ったときには、見たこともない組み合わせの怪獣同士の対決がパッケージに描かれたビデオを発見し、興奮したのを覚えている。大学生になった頃、古本屋で投げ売りされているビデオと再会したとき、なんの疑いもなく一瞬にして心惹かれたのは、そんな経験があったからかもしれない。
その古本屋では、大量のビデオがほこりをかぶり、床に積み上げられていた。まったくといっていいほど映画の知識がなかったが、いま考えると必要もなかったかもしれない。タイトルはまず知らない、ジャケットの絵柄も見たことがない、出ている俳優も知らない、そんなビデオがほぼ100%だったが、よくわからなければわからないほど怪しく輝いて見え、欲しくなった。
その意味で『未来警察マッド・ポリス』(1988年、アメリカ)のビデオ[写真1]は地味ながらポイントが高く、なによりジャケットの表1の人物が2人ともマスクやヘルメットですっぽりと顔を覆っているという、この匿名性に心を掴まれた。映画は有名性で成り立っているものと思っていたので、こういうものは本当に不思議だった。内容も、映画としておもしろいかどうかはわからないが、絶対おもしろいだろうという確信があった。買ってすぐ観てみると、やっぱりおもしろかった。荒廃した世界での、独裁政府とレジスタンスの戦い。そこになぜか美しい女性の姿をしたエイリアンが絡む。なにも知らなかった時期ならではの物珍しさもあったとは思うが、この作品が『マッドマックス2』(1981年、オーストラリア)の影響下にある数多の亜流作のひとつだとわかるいまでも、このテイストが好きだ。

つづいてレーザービームも発射できる改造バイクが出てくる映画『超高性能兵器サイクロン』(1987年、アメリカ)のビデオ[写真2]も、なんとなくジャケットが気になり買ってみると、これもなかなかおもしろかった。この方向でOK、という手応えを感じ、ますますビデオ漁りが加速した。『アメリカン忍者』『吐きだめの悪魔』『片腕サイボーグ』といったタイトルにも、なにか引っかかるものを感じて押さえた。のちに調べると、それらがことごとく1987年に新宿・歌舞伎町の場末の映画館で「ヘラルド・ベスト・アクション」と銘打って連続公開されたB級映画群だとわかり、図らずも自分の好みを認識することになった。

のちに仕事としてブルーレイのデザインを担当させてもらうことになる『ジャイアント・スパイダー/大襲来』のビデオ[写真3]も、その店で手に入れた。この作品は1975年にアメリカでつくられた、いわゆる生物パニック映画で、あまりの出来の悪さゆえに一部で熱狂的なファンを生んでいる。ジャケットの絵が抜群にいい。絵看板を思わせる荒々しいタッチが、この映画のいかがわしさを見事に表現している。のたのたとくねる題字も魅力的だ。この題字が、背のほうではあっさりと、普通のゴシック体に変更されているのもまたいい。このビデオがリリースされた80年代当時、ビデオは買うよりもレンタルが主流だったので、棚差しになったときの背の見えかたは相当重要だったはずだ。このゴシック体は、それを考慮した結果ではなかったか。

ちなみにこうしたアートワークについては作者がわからないのが常だが、このビデオにかんしてはジャケットの表4に「イラストレーション/新井田 孝」とクレジットが入っている。新井田孝さんは官能小説などの艶めかしいタッチの装画で知られ、このビデオの発売元パック・イン・ビデオ(レンタルビデオの初期から数多くのマイナーなタイトルをリリースした)では『ブレイン・ウェイブス/悪夢の生体実験』(1983年、アメリカ)のアートワークも新井田さんが手がけている[写真4]。よく知られる新井田さんの画風は、こちらのほうだろう。邦題よりずいぶん大きなアルファベット表記のロゴ「Brain Waves」は誰か別の人の手になるものかもしれないが、そのデザインを含めて、こちらも『ジャイアント・スパイダー/大襲来』に負けず目を引くジャケットである。

この古本屋のようにビデオが買えるリアル店舗は、ほとんど姿を消して久しく、好事家にとっての探求の舞台はインターネットに移っている。わたしも日々まめにチェックしているが、最近久々に、これはと思うビデオを手に入れた。その名も『アバンチュールはデュエットで』[写真5]。再評価の予感が高まるカルロ・ヴァンツィーナ監督が1983年に撮ったジャーロ映画(イタリア製のスリラー映画)の一種で、主演は『007/ユア・アイズ・オンリー』(1981年、イギリス・アメリカ合作)にボンド・ガールとして出たこともあるキャロル・ブーケ。

ジャケットは、横文字だらけの題名(音楽の日本コロムビアらしい命名センス?)もあいまって、一見してトレンディというか、ある種の趣味のよさが目指されていることがわかる。背景になっているキャロル・ブーケの絵は、海外で描かれたこの映画のキー・アート(メインビジュアル)だ。この絵が周囲に余白をとってレイアウトされていることにも、デザインの上品志向は表れている。絵の前景には、印象的なポーズの主要キャラクター2人が切り貼り。『燃えよNINJA』(1981年、アメリカ)に始まるニンジャ・ブームの影響か、左の男性はヌンチャクをかまえてこの時代特有の香りを漂わせている。ところで右のチャイナドレスの女性(またしても東洋的)は明らかに背景の絵と同じキャロル・ブーケだが、その繰り返しは気にならなかったようだ。
この映画は日本では劇場公開されていない。かわいらしくも洒脱な題字はビデオのために描き下ろされたもので、ジャケットの表4上部にある原題「MYSTERE」の海外製ロゴ、このデザインをひらがなとカタカナに応用している。ちなみに「CAROL BOUQUET」などの俳優名に、事件や調書を思わせるタイプライター系の書体が使われているところにも、デザイナーの細やかな心配りを感じる。
冒頭に記した『VHSテープを巻き戻せ!』の公開時、わたしは雑誌の創刊号でインタビューさせていただいたKプラスの小坂裕司さんと一緒に、上映を観にいった。小坂さんは当時すでに「ビデオ博物館」としてインターネットでVHSビデオのレンタルをしており、現在も根気よく取り扱いタイトルを増やし続けている。
映画の上映後にはイベントがあり、ゴミビデオ、クズビデオなどと呼ばれるどうしようもなく出来の悪い映画をおもしろおかしく紹介していた。小坂さんとわたしは、食事をしましょうということでイベントには参加せず、映画館をあとにした。道を歩きながら小坂さんが「わたし、ああやってビデオをバカにしたり、そういうのあんまり好きじゃないんですよね」と静かに言った。B級映画にツッコミを入れるという、『スクリーム』(1996年、アメリカ)でも描かれた鑑賞スタイルがカッコいいと思っていたわたしにとって、この小坂さんの発言は衝撃だった。つくり手が真剣につくったものを、なぜ笑うのか。
もちろん、イベントをやっていた人たちに悪意はなく、その人たちなりのビデオへの愛情表現だったと思う。が、それ以上に、考えたこともなかったその問いかけに、針でチクッと刺されたような気持ちだった。いまでもわたしは、あんまりな映画を観ると、つい笑ってしまう。だっておもしろいのだから、仕方がない。しかし小坂さんの言葉を聞いてから、わたしのなかに変化もあった。ビデオジャケットのデザインは、明らかに不出来なものやバカバカしいものも、いまでもあいかわらず楽しいと思うが、きちんと仕上がった、真面目なデザインもいいと思うようになった。
『ジャイアント・スパイダー/大襲来』にも『アバンチュールはデュエットで』にも、ある種の真剣さがある。それゆえの妙な感じもたしかにある。もちろん、数あるビデオジャケットのなかには投げやりな仕事もあるだろうが、それも含めてこの頃のビデオはいい。いまわたしが一生懸命にデザインをすると、こうはならない。だからこそビデオには憧れる。
桜井雄一郎(さくらい・ゆういちろう)
本のデザイナー。映画/VHSの自主雑誌『南海』編集人。鈴木一誌デザイン事務所を経て独立。編著書に『映画広告図案士 檜垣紀六 洋画デザインの軌跡』(檜垣紀六著、佐々木淳と共編、スティングレイ)。最も最近の仕事はミムジー・ファーマー主演映画『MORE/モア』『渚の果てにこの愛を』の宣伝美術。
公開:2021/10/28
 84
84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳
 83
83ワールドワイドウェブのこと/永原康史
 82
82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3
/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81
81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩
 80
80数学と計算機と美学/巴山竜来
 79
79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生
 78
78ひび割れのデザイン史/後藤護
 77
77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史
 76
76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子
 75
75日本語の文字/赤崎正一
 74
74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子
 73
73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部
 72
72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳
 71
71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史
 70
70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子
 69
69作り続けるための仕組みづくり/石川将也
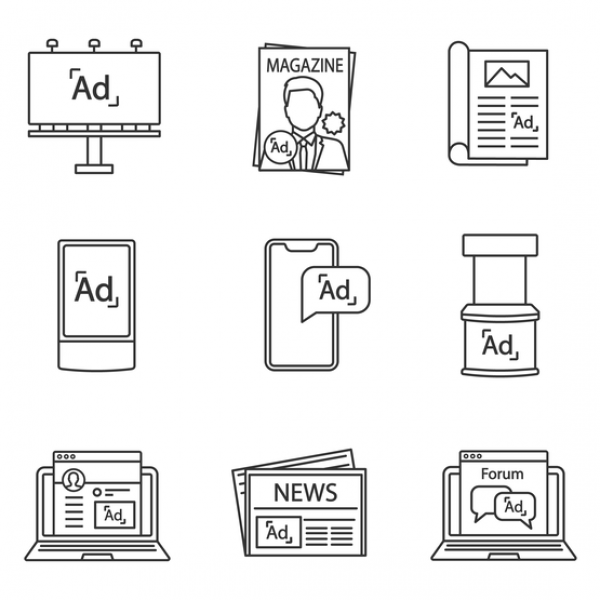 68
68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子
 67
67音楽の空間と色彩/赤崎正一
 66
66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳
 65
65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩
