「日本のグラフィックデザイン」を更新すること

2016年から2年間、DNP文化振興財団から研究助成を受け、ニューヨークのクーパー・ヒューイット・スミソニアン・デザイン・ミュージアムに所蔵されている日本のポスターを調査したことがあった。日本のグラフィックデザインがどのような経緯で海外に渡り、美術館に収蔵されているのかに関心があったからだ。詳細な内容についてはここでは割愛するが、私がこの調査研究で一番興味深いと思ったのは、対象となった「日本のグラフィックデザイン」として分類されている作品のなかに、2000年代以降の作品がなかったことだった。所蔵されているものを見ると、その多くが80年代、90年代に制作されたもので、所蔵年でいうと90年代が一番多い。作家別に所蔵作品の数を見ると、松永真や田中一光、横尾忠則の作品が上位3位をしめる。なかにはデザイナーが不明なものまであった。これら作品全てがコレクターやギャラリー、あるいはデザイナー本人からの寄贈で、購入はひとつもなかった。収集の方針に戦略性があるわけではなく、偶然性が高い印象を持った。この結果には、少々驚いたが、その一方で妙に納得する部分もあった。というのも日本のグラフィックデザインを取り扱った英語の書籍で見るのは大抵、田中一光や亀倉雄策といった言わばグラフィックデザイン史上の人物による作品で、その多くが90年代以前に生み出されたものばかりだからだ。最も知られている作品といえば、田中一光の「日本舞踊」と亀倉雄策の「東京オリンピック」だ。細かく説明せずとも、その絵が浮かんでくる人は多いだろう。
海外のデザインコミュニティと話をしていても、90年代までの情報がまだ海外における日本のグラフィックデザインのイメージを支配している印象が強い。これもまたニューヨークでの話なのだが、2018年にクーパー・ユニオン大学付属のハーブ・ルバリン・スタディセンター・オブ・デザイン・アンド・タイポグラフィの協力のもと「Representing Graphic Design in Japan(日本のグラフィックデザインを更新すること)」(図1)というトークイベントを行った。その際、事前にTwitter上で、「日本のグラフィックデザインと聞くと何を思い浮かべる?」という質問を投げかけたところ、その答えの多くは、福田繁雄、田中一光、横尾忠則で、若手のデザイナーを上げた人は少なかった(図2)。また、ディスカッションのゲストとしてポスターハウスのキュレーター、アンジェリーナ・リッパートにも登壇してもらい、彼女が関心を寄せる日本のデザインについても話を聞いたが、ここで上がったのも80年代、90年代のポスターだった。アメリカでポスターというと、街中で貼られてもすぐに剥がされたり、上から他のポスターを貼られてしまうために安価に制作されるのが一般的だが、対して日本のポスターは、グラフィックや用いられる写真の美しさへのこだわりが凄まじく、さらにはそれを高める印刷・加工技術は目を見張るものがあるらしい。特にバブル期のポスターは、その最高峰なのだという。
現在でも国内外のグラフィックデザイン関連団体の交流は続いているし、日本のデザイナーやデザインの展示が世界のどこかで開催されているという話は耳にする。けれども、だからと言って海外で日本のグラフィックデザインに対するイメージが一様に更新されているわけでもないようだ。
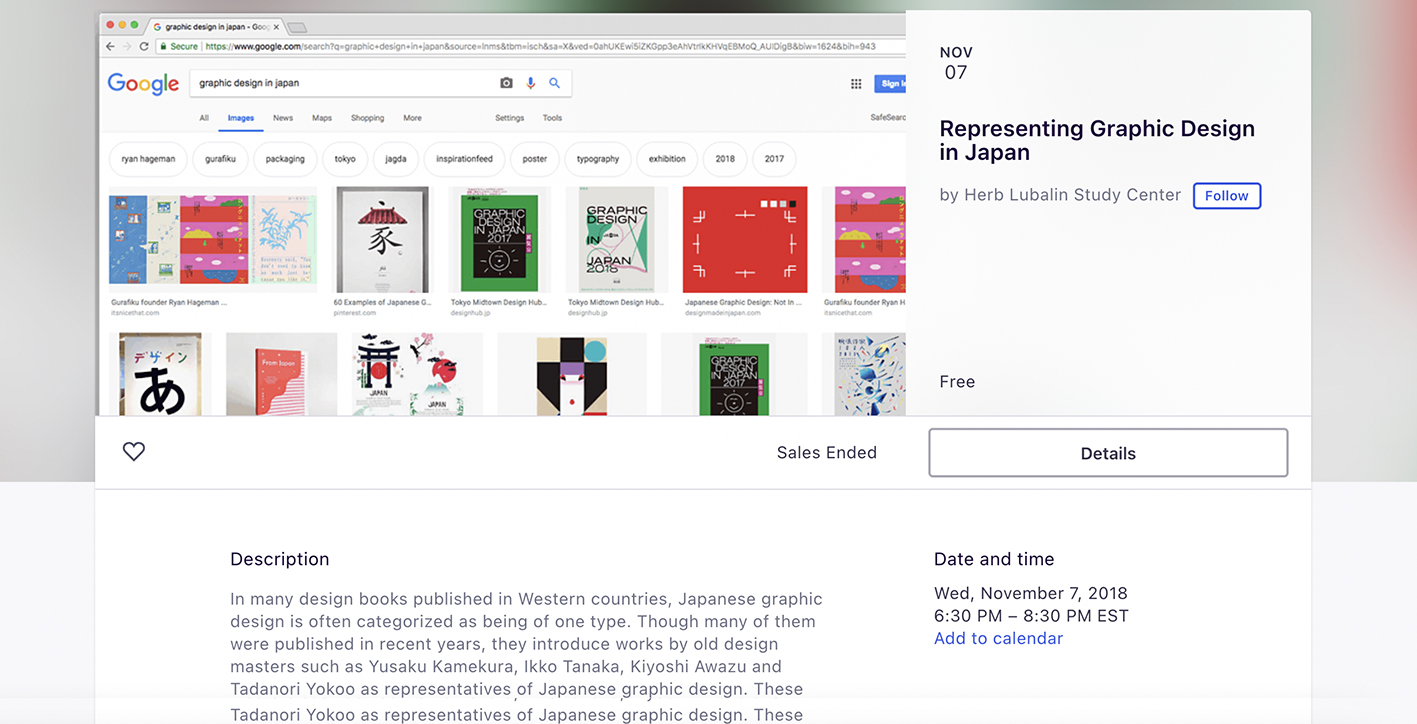

日本のグラフィックデザイン界が海外交流を本格的に始めたのは1950年代だ。日本宣伝美術会の設立と同時に日本において宣伝美術が分野として確立し、そこからどんどんと海外での存在感を高めていった。1960年代は、日本のグラフィックデザイン史の黄金期だ。60年の第一回世界デザイン会議や64年の東京オリンピックのデザインプロジェクトを通じて、日本のグラフィックデザインは世界での立場を確実にした。高度経済成長期における日本のグラフィックデザインの、とくに広告分野での躍進は目覚ましい。日本人デザイナーが国際的な公募展で賞を獲り、海外での個展を実現させている。80年代後半には、ついに日本で初めてのポスターの国際公募展である世界ポスタートリエンナーレトヤマが開催されるにいたる。当時の文献や資料を読むと、日本のグラフィックデザイン業界が一致団結し、世界に発信しようとしていたことがわかる。海外での評価が国内での評価につながっていた時代だ。国内で一流と呼ばれるには、国外での個展開催や美術館での収蔵実績、国際的なデザイン機関への参加が必要不可欠だった。クーパー・ヒューイットに集まっている「日本のグラフィックデザイン」の一部もその流れに乗って辿り着いたものなのかもしれない。
『JAGDA年鑑’92』に掲載されている永井一正と福田繁雄の対談に面白いことが書いてあった。両氏によると、日本のグラフィックデザインの世界での評価は高いが、それまでのように日本のグラフィックデザインが海外のデザイナーを刺激することは少なくなり、「日本のデザイン」ではなく、個々の作家性が要求されているのだという(図3・4)。一種の達成感を持つ一方で、さらに高みを目指すのではなく、違うベクトルで日本のデザインを考えていこう、それまでとは違うスタンスで日本と海外の関係性を考えよう、という意識の変化が読み取れる。90年代前半に世界における日本のグラフィックデザインの評価がある程度定まった時点で、海外への発信や国外のデザイナーとの交流がスローダウンしていったのだろうか。だとすれば、クーパー・ヒューイットで私が目にした「日本のグラフィックデザイン」が90年代で止まっている理由にもなる。
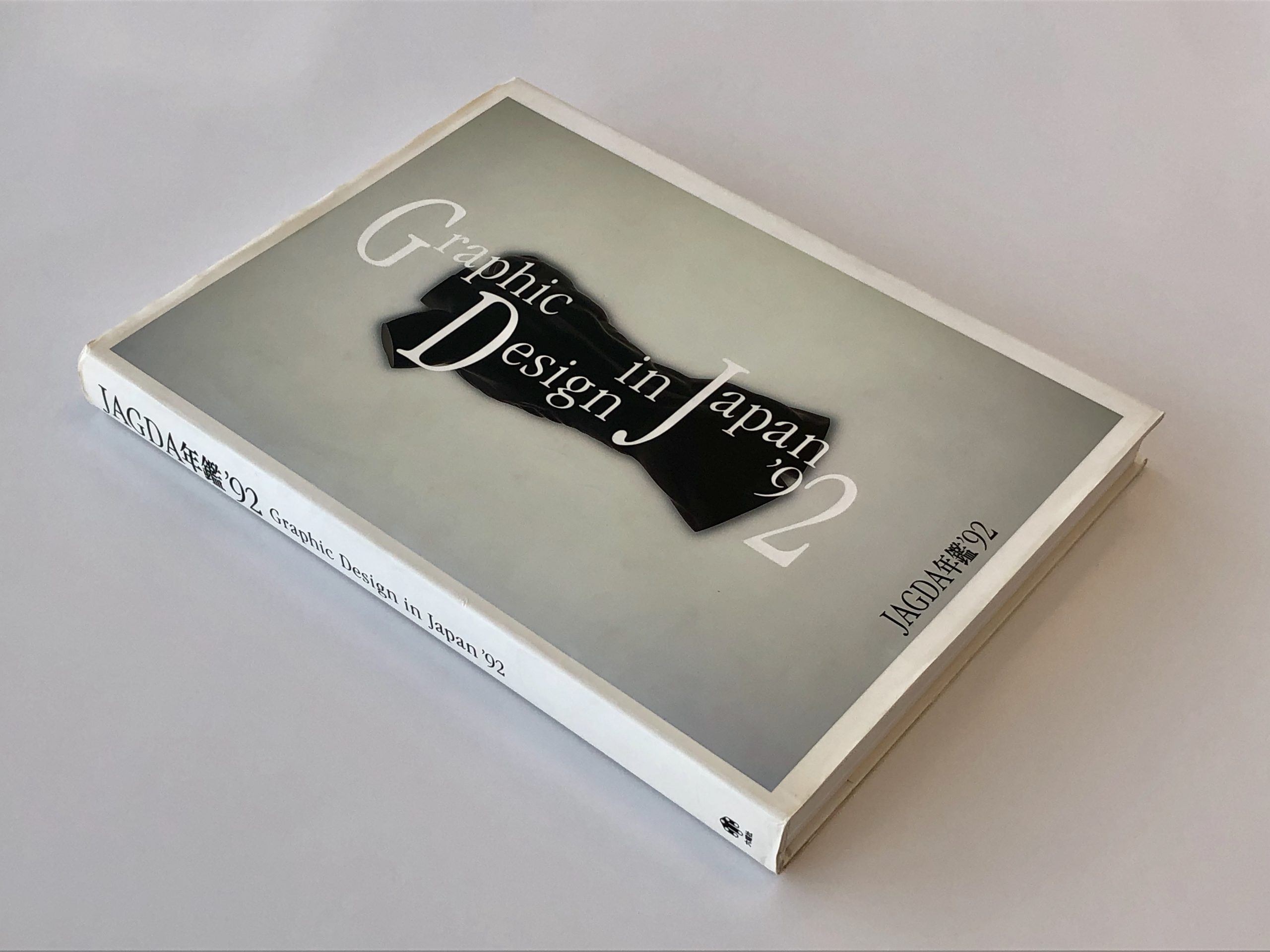

余談だが、90年代といえば数々のポスター展が国内の美術館で開催されていた時期でもある。私が所属する東京国立近代美術館の過去の展覧会実績を見ても、この頃はポスター展と名のつく展示が毎年のように開催されており、その後に館に収蔵された作品が多くある。もちろんポスター展自体を珍しいといっているのではない。アールデコやアール・ヌーヴォー様式の表現が見られるものやポーランドのポスターのように、その希少性や表現の独自性などが歴史的な文脈で解釈されるものは、それまでも展示の機会があった。しかし、国内の現役デザイナーの個展を開催することは、東京国立近代美術館の長い歴史においても90年代までは例がなかったのだ。96年の亀倉雄策のポスター展を皮切りに、福田繁雄、永井一正、田中一光のポスターの個展が毎年続いた。そして2000年代になってぱたりとポスター展は開催されなくなったのだ。海を超えて遠く離れた2つの美術館に着目して、同じキーワードが浮かび上がってくるのは単なる偶然なのだろうか。90年代、ポスター、そして美術館という組み合わせは何かもっと深い意味を持っているように思えてならない。これについては推測の域を越えることがないので、このあたりで話をやめておこう。
私の体感としては2010年代以降、個人で海外に向けて情報を発信したり、入手することがインターネットの普及でずいぶんと容易になり、活発になったように思う。それに伴い、自分も含めてであるが、個人単位で国内外のデザイナーと接する機会を持つ人が増えたように思う。
まず頭に浮かんだのは、私が通訳として参加した「グラフィズム断章:もうひとつのデザイン史」展(開催地:クリエイションギャラリーG8、2018年)の関連トークに登壇していたフランスのデザインスタジオdeValenceを運営するアレクサンドル・ディモスの活動だ。自身のスタジオで運営する出版部門B42から刊行されている雑誌『Back Cover』6号(図5)で日本の視覚文化特集を行った。彼は特集の冒頭で、ヨーロッパでは日本のグラフィックデザインのイメージが更新されていないことを指摘しており、自身の目で現状を見ることの必要性を語っている。ディモスは服部一成、寄藤文平、高田唯といったグラフィックデザイナーだけでなく、ウルトラマンのキャラクターや漫画「のらくろ」などにも関心を寄せる。なかでも友禅染の作家、森口邦彦の名前を挙げたのには驚いた。森口は元々グラフィックデザインを学んでおり、その経験を活かして、幾何学的な造形が特徴的な着物の図案を考案している。私は美術館の工芸課に所属しているので、日々の業務でこの作家の作品を知っていたものの、グラフィックデザイン界隈でその名を聞くことはそれまでなかった。独自の視点で日本の視覚文化への関心を広げ、解釈を構築している例だといえよう。

もうひとつ紹介したいのは、アメリカ人のデザイナー、ライアン・ヘイグマンが個人で運営する「Gurafiku」という日本のグラフィックデザインを紹介するサイトだ。もともとは自身が関心のある日本のデザインを中心に紹介を始めたそうだが、以前メールをやりとりした際には、歴史的な流れも踏まえつつ、もっと包括的なアプローチで掲載する作品を選ぶようにしていると言っていた。そういえば、クーパー・ヒューイットでの調査研究をしていた際に、日本人デザイナーによるいくつかの作品が、「Gurafiku」をきっかけに所蔵されたことが分かった。キュレーターの1人が展覧会に出品する作品を調査していた際に、このサイトで見つけたポスターに関心を持ち、その作家に展覧会への出品を依頼。後に出品作品がミュージアムのコレクションになったのだ。掲載された情報の正確性については色々と議論の余地があるのだが、個人のサイトが情報源として機能していることを示す例だといえる。実はこの記事を執筆した際に久しぶりにサイトを訪問してみたのだが、更新が止まっていた。日本のグラフィックデザインを日々更新することの難しさをここでも見つけることになるとは思いもしなかった。
情報発信と受容のチャンネルが増えたことにより、より様々な立場の人の考えや意見に触れることができるようになったが、その反面、グラフィックデザインに関する国内外の言説の把握や共有が難しくなってしまっている状況があるように思う。特定の雑誌や書籍が情報源として機能し、みんなが同じ情報を参照していた時代は遠い過去の話になった。昨日SNS上を賑わせていたデザインは、いつの間にか跡形もなく消え、今日はまた新しいデザインが更新される。自分が見ている情報を他の人が見ているとは限らないのだ。
野見山桜(のみやまさくら)
2016年、ニューヨークのパーソンズ・スクール・オブ・デザインにてデザイン史の修士号を取得。デザインの研究者として展覧会の企画や書籍・雑誌への寄稿を行う。東京国立近代美術館工芸課客員研究員、女子美術大学・東北芸術工科大学非常勤講師。
公開:2021/07/05
 84
84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳
 83
83ワールドワイドウェブのこと/永原康史
 82
82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3
/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81
81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩
 80
80数学と計算機と美学/巴山竜来
 79
79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生
 78
78ひび割れのデザイン史/後藤護
 77
77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史
 76
76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子
 75
75日本語の文字/赤崎正一
 74
74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子
 73
73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部
 72
72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳
 71
71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史
 70
70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子
 69
69作り続けるための仕組みづくり/石川将也
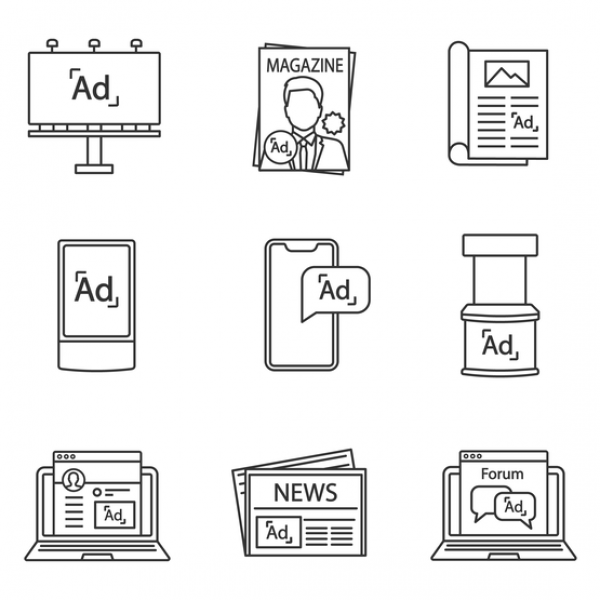 68
68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子
 67
67音楽の空間と色彩/赤崎正一
 66
66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳
 65
65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩
