思想としてのイラストレーション
─「没後20年 真鍋博2020」展によせて

イラストレーター真鍋博(1932–2000)の没後20年を記念する大規模な回顧展が、2020年10月1日から11月29日にかけて愛媛県美術館で開催された。学生時代の習作から代表作まで、真鍋の多分野にわたる制作活動が展示された同展は、規模、内容ともに近年まれにみる充実したものとなっていた。同展を通じて真鍋博という存在について考える。
日本において1960年代は宇野亞喜良、横尾忠則、水森亜土などさまざまなメディアを横断するイラストレーターたちが多数登場した時代だった。真鍋博もまた、同時期にそのような活躍ぶりを見せた描き手のひとりとしてあげられるだろう。挿絵、広告、アニメーション、舞台装置、エッセイなど幅広い仕事をこなしながら、2000年に68歳でこの世を去るまで旺盛な活動を展開した。以下では昨年愛媛県美術館で開催された「没後20年 真鍋博2020」展を中心に、そんな真鍋について考えてみようと思う。
真鍋の出身地でもある愛媛県の愛媛県美術館と愛媛県立図書館には、遺族により約28,600点ものコレクションが寄贈されている。「没後20年 真鍋博2020」展は、それらを活用し構成されたものである。彼は高度成長や大阪万博を背景に盛り上がりを見せた「未来ブーム」の主要なイラストレーターとして知られ、星新一や筒井康隆をはじめとしたSFの挿絵や装丁も手がけている。よって、展示でもそんな未来予想図的なイラストレーションを多数見ることができるのだが、これらは子細に観察すると木々が配されていたり、自動車だけではなく自転車も走っていたりと、真鍋が未来を多様性を包摂するひとつの「環境」として構想していたことが分かるだろう。

その他の出品作についても見どころは多かった。シュルレアリスム風のモルデカイ・ロシュワルト『レベル・セブン:第七地下壕』(弥生書房、1960年)の挿絵は、1960年に第1回講談社さしえ賞を受けた仕事である。当時は和田誠や灘本唯人といった広告業界のイラストレーターたちが出版業界に進出する以前であり、まだ岩田専太郎ら挿絵画家が存在感を持っていたころだった。そうした時代にこのような洗練された絵柄で評価を得た同作は、真鍋の先駆性を証拠立てる重要な成果だといえるだろう。細く均一な描線のイラストレーションの描き手といえば、上の世代では山名文夫が代表的な存在として思い当たるが、真鍋の描線には独特のクールな洒脱さが備わっている。このようなスタイリッシュさは、1966年から79年にわたり担当した『ミステリマガジン』(早川書房)の表紙のフォトコラージュでも存分に発揮されている。
松本清張『黒い福音』(中央公論社、1961年)の装丁は、黒のビニール装で背にタイトル、著者、出版社を記し、表紙に十字架を思わせるマークを金で箔押ししただけのシンプルな仕上がりだが、緊張感のある佇まいが目を引く。イラストレーターの池谷伊佐夫は真鍋による推理小説の装丁について「おどろおどろしいビジュアルの多かったこの世界の装丁に斬新な風を吹き込んだ」[*1]と述べている。当時の「おどろおどろしいビジュアル」とは、おそらく年代的にはカストリ雑誌の流れを引き継ぐ『裏窓』(久保書店)などに掲載されたような絵柄を指しているのだと推測されるのだが、ここからは絵を描くことにこだわらず、クレバーにデザインに向き合う真鍋の姿勢が浮かび上がってくるだろう。全体として展覧会は時系列とメディアを上手く整理しながら、真鍋のイラストレーターとしての発想の豊かさや、デザイナーとしての手腕の確かさを伝えることに注力されていた[*2]。

このように充実した成果をあげてきた真鍋であるが、デザイン、挿絵、漫画、児童出版美術といった多様な文脈が混ざりあっていた60年代のイラストレーションのなかで、彼の存在はどのようなものだったのだろうか。真鍋はイラストレーターとしての活動を本格化させる以前、当時の前衛美術の中心だった読売アンデパンダンに参加するほど美術家としての活動を積極的に行っていた。筆者はこうした経験が、彼のなかで表現についての批判精神を育むことにつながったのではないかと見立てている。真鍋が他のイラストレーターと異なっていたのは、最終的に印刷された成果物を「作品」と呼び、原画を「図面」「設計図」と位置づけるような明確な思想性である。「イラスト空間に発射せよ」という文章のなかで彼は、イラストレーターは平面への印刷だけではなく、凹凸のある物体や建築にも対応することで、「印刷への戦いをメディアの戦い」へと置き換えることができるのだ、と述べている。こうした雄弁さは横尾忠則とも共通しているが、同時代を意識した横尾のそれに対し、真鍋の言葉はより即物的な印刷技術に即したフォーマルな立脚点から出発している。
そのように考えると、真鍋の思想は粟津潔のいう「グラフィズム」にニュアンスが近いように思えてくる。粟津の提唱するグラフィズムとは、さまざまな複製物そのものがオリジナルとしてみなされる現代の様式のことを指している。ここでは印刷物のみならずインダストリアル・デザインや映像メディアもグラフィズムのなかにあるものとされているのだが、こうした複製物を原画よりも重要視する立場は、真鍋とも共通のものであるといえるだろう。彼の印刷に対するこだわりには並々ならぬものがあり、印刷所の職人たちは真鍋に校正刷りを出すと、数多くの指示が書き込まれ、真っ赤になって返ってくると語っている。

「没後20年 真鍋博2020」展は、真鍋のキャリアを紹介するまたとない機会となっていた。同展だけではなく、愛媛県内の他3カ所で関連する展覧会をほぼ同時期に開催したその力の入れようは、イラストレーターの回顧展としては国内過去最大級の規模だったと思われる(筆者が訪れることのできた愛媛県美術館と愛媛県立図書館だけでも合計の展示総数は1,072点に上る)[*3]。しかし欲をいえば、より社会的な広がりを持つテーマを部分的にであれ設定しても良かったのではないだろうか[*4]。なぜなら真鍋はイラストレーションについてのみならず、文明批評的なエッセイをいくつも残しているし、彼の描く未来像には(原子力も含めた)エネルギー問題への視点が伴っている場合もあるからだ。福島第一原発の事故を経験した私たちにとって、高度成長期のエネルギー表象について振り返ることの重要性は論をまたない。愛媛県の膨大な「真鍋博コレクション」を利用した研究の進展、および意欲的な展覧会の企画に今後も期待したい。

註
*1
池谷伊佐夫「真鍋博の装丁雑感」『日本古書通信』860号、日本古書通信社、2001年、p. 4
*2
デザイナーとしての真鍋に関しては、次の動画でタイポグラフィーなどについて興味深い言及がなされている。
真鍋真・五味俊晶・松村大輔「『真鍋博の世界』刊行記念LIVEトークイベント」
https://www.youtube.com/watch?v=AcI57pNrmeU
*3
愛媛県美術館の他に開催されていたのは、愛媛県立図書館「真鍋博のイラストカバー 文庫本」展、新居浜市美術館(あかがねミュージアム2階)「真鍋博の贈りもの」展、セキ美術館「真鍋博と印刷会社」展の三つの展覧会である。
*4
愛媛県立図書館での展示でもそれは同様であり、実見することのできなかった新居浜市美術館とセキ美術館の展示でも、筆者の調べる限りでは、社会的な観点からの展示が行われた形跡は確認できなかった。
参考資料
粟津潔『デザイン夜講』筑摩書房、1969年
竹内孝治『真鍋博の未来都市観に関する研究 —都市住居の新たなビジョン構築に向けて—』都市のしくみとくらし研究所、2012年
真鍋博『真鍋博ORIGINAL 1975』講談社、1975年
横尾忠則編『復刻版:現代のイラストレーション』誠文堂新光社、1987年
『「真鍋博展」図録』朝日新聞社、2004年
『真鍋博の世界』パイ インターナショナル、2020年
塚田優(つかだ・ゆたか)
視覚文化研究、多摩美術大学研究員。2014年、『美術手帖』第15回芸術評論募集に「キャラクターを、見ている。」が次席入選。美術、イラストレーション、アニメーションを中心に各種媒体に寄稿を行う。主な論文は「日本デザイン史におけるイラストレーションの定着とその意味の拡大について——1960年代の言説を中心に」『多摩美術大学研究紀要』第34号、2020年
公開:2021/01/29
修正:2021/10/14
 84
84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳
 83
83ワールドワイドウェブのこと/永原康史
 82
82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3
/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81
81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩
 80
80数学と計算機と美学/巴山竜来
 79
79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生
 78
78ひび割れのデザイン史/後藤護
 77
77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史
 76
76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子
 75
75日本語の文字/赤崎正一
 74
74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子
 73
73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部
 72
72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳
 71
71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史
 70
70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子
 69
69作り続けるための仕組みづくり/石川将也
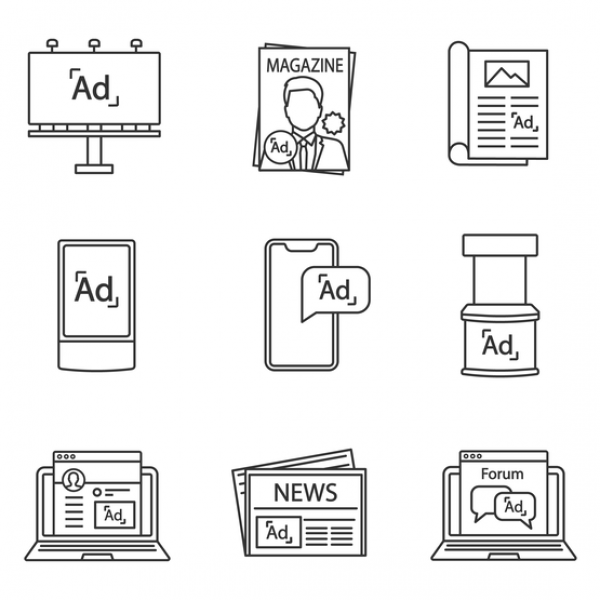 68
68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子
 67
67音楽の空間と色彩/赤崎正一
 66
66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳
 65
65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩
